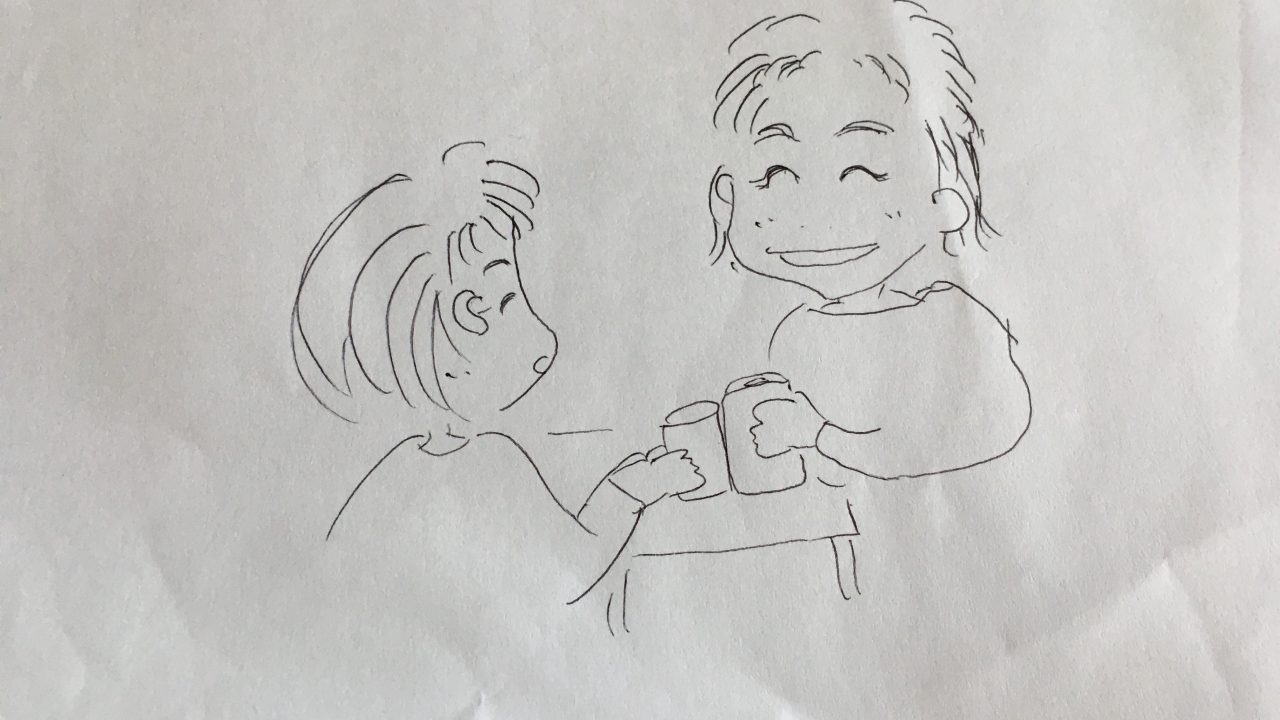最近は片付けばかりをしているので、過去にもらった名刺や学生時代に書いた論文などが見つかり、当時の記憶が蘇ってきた。論文はさすがにとって置いているが、その他はすべて手放した。不思議なもので、手放すと却って記憶が戻ってきて、今になって思い出すことができるようになった。
私は学生時代は臨床心理を学んでいて、論文は「精神障害者のエンパワーメントの意味」について書いた。論文を読み返すと、20代前半の私にしてはかなり完成度が高いものを仕上げていて面白かったので、次回以降にブログに載せたいと思う。
卒業後も、精神障害の方やその支援をしている方とのつながりがあった。中でも特に印象に残っているのが、北海道の南の方で支援を行なっているNさんとの出会いだ。Nさん自身も精神障害を持っていて、同じ境遇にいるピアとしての役割を持っている。私が道南へ泊まり込みに行った時に、Nさんが私の介助をしてくれた。ちょうどその頃、私は障害者として障害者の支援をしたいと思っていても、「障害者だからって、相手のことをわかることができるのか。却って、自分の経験が邪魔をして、押し付けてしまったりしないだろうか」と悩んでいた。
夜が更けて、畳の部屋でオレンジの光の中、二つ布団を並べて床につきながら、Nさんが関わったアルコール中毒の方の話を聞いた。
その方は長いアルコール中毒の期間を経て、その積み重ねにより余命を告げられるほどの病気を抱えていた。アルコールをこれ以上飲んだら生命が危ないため、医師からもアルコール禁止を強制されていた。過去に路頭に迷い支援者もいなかったが、Nさんを踏めた支援者も応援してくれている状況だった。本人にとっては「やっと」安心できる状況になったのかもしれない。しかし、その時には、余命宣告をされていた。
ある晩、Nさんはその人に呼び出された。確か、その人の誕生日だったかもしれない。
「今日は、一緒にお酒を飲んでほしい。」
そう言われたNさんは、一瞬ためらったが、お酒を飲む時間をお伴したという。多くの支援者は「お医者さんから飲まないようにと言われているので、付き合えない。」と言うだろう。半分相手を気遣っていて、半分は自分の責任を問われるからだ。Nさんは、その人の時間がどんな風に流れていったのか、その流れを経て、今の本人が何を望んでいるのかを一番に考えた対応をした。お酒の缶で乾杯し、夜な夜な、お酒を付き合ったのだ。
「ありがとう。良い時間を過ごした。」と穏やかに話していたという。
後日、息を引き取った。
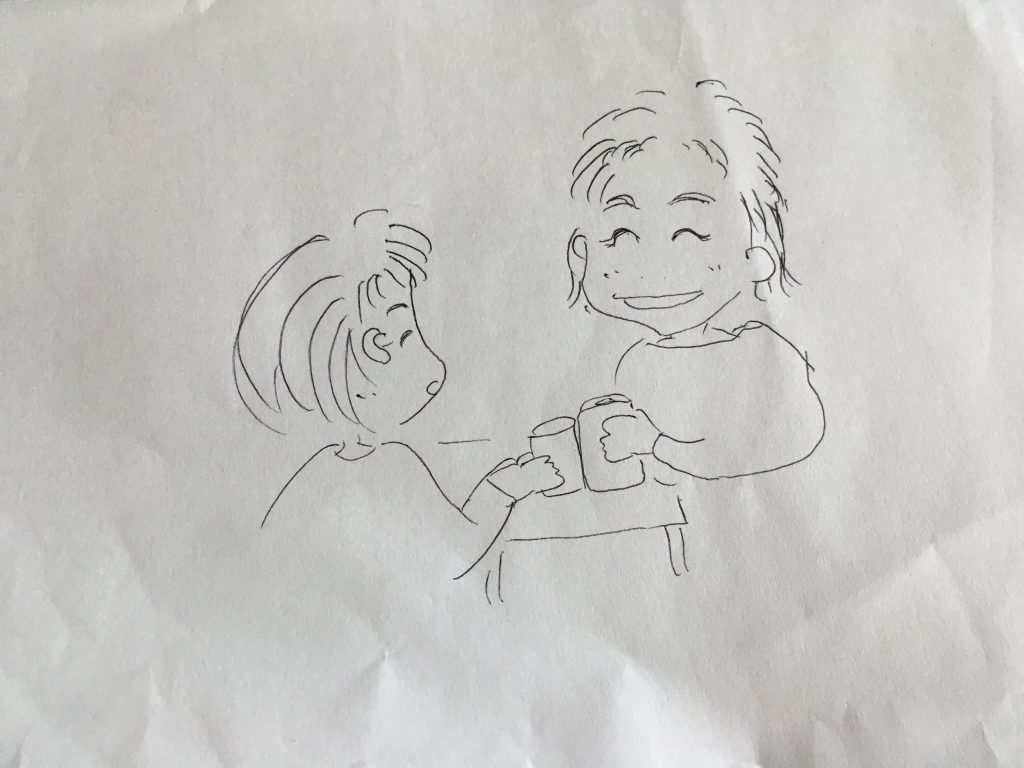
私は、その話を聴いてから、「支援」と表現することのおこがましさを感じずにはいられない。その人はお酒をたとえ飲まなかったとしても、いつかは息を引き取っていた。やめられないお酒を「良い時間」で、誰かと楽しんだことは、紛れもなく本人の最後の幸せだったかもしれない。Nさんは葛藤しながらも、その人の選択を尊重したのだと思う。
Nさんとしばらく会っていないが、どうしているだろうか。