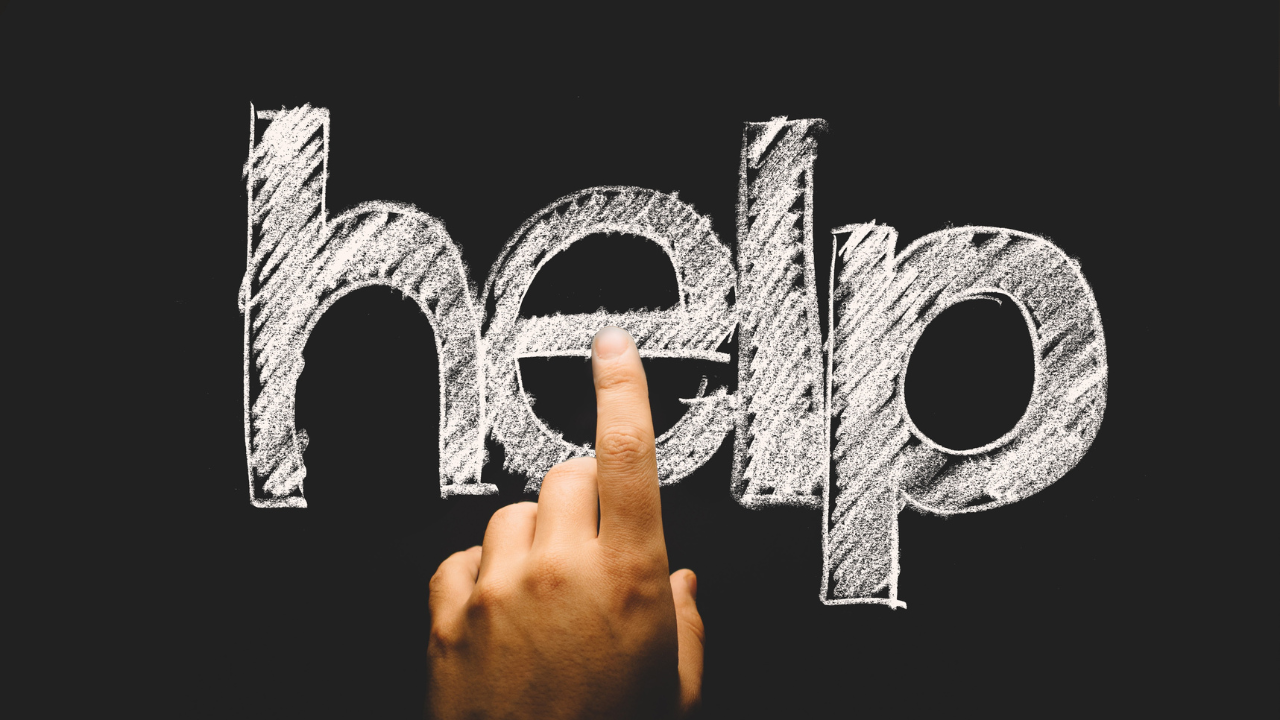みなさん、お元気ですか。いつも読んでくださりありがとうございます。これを読んでいる人の中には、障がいのある人、その家族の人、障がいのある人のサポートをしている人など、いろいろな人がいると思います。
今回は、だれにでも関係することについて考えてみたいと思います。
それは、「だれかに手伝ってもらうことは迷惑ですか」ということです。
目次/Contents
「迷惑をかけている」と思ってしまうのは、どうして?
私は、子どものころから、トイレや着替えなど生活のことすべてに介助が必要なので、いつも人に何かをお願いしてきました。そのように、人に手伝ってもらうときに、いつも感じていたのは「ごめんなさい」「申し訳ない」「迷惑をかけているのではないか」という気持ちでした。
どこから、そういう気持ちが生まれてきたのでしょうか。私は、大人になってから、ようやく振り返られるようになったんですが、周りから聞こえることに影響されていたんだと思います。たとえば、「人に迷惑かけちゃダメだよ」と先生に言われたり、幼い私を病院に連れて行ったときに、親が「お世話になります」とか「申し訳ありません」と支援者に言っているのを耳にしたり……。
私の場合、小学校に入学するときも、普通小学校へ行こうとしたら「あなたは養護学校じゃないといけません」と教育委員会の人に言われたり、校長先生に直接交渉したら「母親が付き添うならいいですよ」と許可をもらう形での入学だったりと、「ありがとうございます」と頭を下げざるを得ない状況でした。
「しかたない、特別にいいですよ」と一方的に言われるのは、小学校入学のときだけでなく、その後もいろいろな場面でありました。福祉サービスを受けるときでさえも、ヘルパー事業所の責任者の方やヘルパーさんに言われることもあったので、ごく普通の生活のことさえも、肩身の狭い思いをしていかないといけないの?と疑問に思うこともありました。
つまり、
これまで聞いてきた、ささいな言葉が積み重なって、知らないうちに「自分は迷惑をかける存在なんだ」と思わされてきたんだと思います。
日本は「迷惑をかけないようにする文化」があると思います。それはいい面もありますが、いつのまにか私たちの心に取りついて、「他の人よりできないことが多い人」のことを「迷惑だ」と言ってしまう、思ってしまう雰囲気がつくられてきたのでしょう。
福祉サービスを利用すると、後ろめたい?
その「迷惑をかけない」という言葉は、自分や家族に対しても、悪い影響があります。福祉サービスを受けようとするときに、役所に申請をしに行かなければなりませんが、そのとき「お世話になる」という意識が心のどこかに出てきませんか。
つまり、
「自分で、自分のことができなくなった」
↓
「助けてください。お願いします」
という気持ちです。
幼いころからいつも人の手が必要な私でさえも、長い間、「自分ではできないから、お世話になります」という思いでした。だから、なにもできない自分が情けなかったし、トイレ介助をお願いすることすらも、「今、頼んでもいいですか」と人の顔色をうかがっていたんです。その状態を続けていくと、トイレは生理現象なのに我慢したり、人に頼むことが恥ずかしいと思ったり、自分が生きていることにも自信をなくしたりしてしまいます。
さらに、本人だけではなくて、その家族が「うちの子が迷惑をかけている」「うちの親が介護にお世話になる」といったような「希望がない」という気持ちになってしまう人が少なくありません。
そういう気持ちになってしまうこと自体は、何も悪いことじゃありません。
ただ、遠慮したり、我慢したり、「ありがとう」が口癖になったりしたときに、自分の気持ちに手を当てて、「苦しくない?」「どうして暗い気持ちなの?」「本当は、こんなに我慢したいの?」と自分に質問してみてください。
私の場合は、大学生のときや、社会人になって、いろいろな人と出会ったときに「どうして、そんなにお礼ばかり言うの?そんなに言う必要ないし、障害のない人はそこまでお礼を言わなきゃなんて思っていないよ。」と友人に言われたことがあります。そのときに、初めて、ハッと気がつきました。
色々な人に会って「できないことは人に任せる」ということを知る
だから、少し立ち止まって、考えてみてほしいです。福祉サービスが必要だからといって、自分に自信をなくしたり、人生をあきらめるのって、もったいない。むしろ、だれかの手を借りたり、サービスを利用したりすることで、「いつものように、私らしく暮らしていく」「やりたいことをやってみる」と考えたほうが、気持ちが明るくなりそうです。本当は希望があることなんです。
つまり、
「自分の残っている力で社会で〇〇がしたい!」
↓
「だから、できないところは他の方法で補いたい」
という発想です。
正直言うと、学校の先生や、福祉で働いている人の中で、こういう発想で話してくれる人は、ほとんどいません。もし、教えてくれる人がいたとしたら、その人は海外の人とお付き合いがあったり、自分の気持ちに正直に行動してきたり、自分と社会の関わりを考えたりしている人だと思います。
私の場合、少し前の話ですが、セクシャルマイノリティの立場にいたヘルパーさんが私の介助に入っていて、そのヘルパーさんがいろいろなことを教えてくださいました。「社会は、男女という2つの性しか考えていない社会であって、そこに当てはまっていない人はいつも、その考え方の人に会うたびにNo.と言って、自分のことをわざわざわかりやすく説明しなければならない」ことが、とても大変であると、そのヘルパーさんは話していました。だから、私の障害者としての苦労も理解してくださり、私はそのとき初めて救われました。
さらに、ヘルパーさんの中には、アフリカ人の方も何人かいました。アフリカでは、家族の人数が多かったり、家がとても大きかったりするので、掃除をする人や子守りをする人を雇うのはめずらしくないそうです。障害者のヘルパーという仕事も、それと同じように、特別なことではなく「できないことを手伝う」というだけなので、「手伝ってあげる」とか上から見下げられることは一切ありませんでした。「あなたが必要なことは何か」をシンプルに聞いていたのが印象的でした。
福祉サービスのしくみは、みんなのためにある
中には「税金がかかっているから、福祉サービスを使うのは後ろめたい」と思っている人もいます。私もそう思っていたときもありましたが、それは、狭い考え方だと思います。今まで私のところで働いてきたヘルパーさんを見ると、「利用者が後ろめたさを感じる必要はない」ということに気がついたんです。
ヘルパーという仕事が国で保障されることで、人が生きるためのケアができる人が増えていくし、それを副業にしながら、他のやりたい仕事をできるようにもなります。
私もヘルパーを毎日利用していますが、私自身はお金をもらうわけではありません。人の手を借りて、日常生活を送ることができ、外に出てスーパーで買い物したり、ボランティアとして日本語を外国人に教えたり、近所の人と話したり、学生に福祉のことを教えたり、友人の相談に乗ったり……と社会で生きることができます。
ヘルパーは、お金を得て、生活したり、家族においしいものを買ったり、新しい勉強や趣味を始めたりできます。
さらに、ここがもっと重要です。「人の生活をサポートするスキルを身につけていく」ということです。これは、ゆいいつ無くならない仕事のうちの一つだと思っています。
そういった仕組みを国が公費で維持してくれているのです。
だから、福祉サービスを受ける人だけが「自分はダメだ」と自分を責めたり、自信を無くしたりする必要はないんです。
もっと広く考えて、長い期間でどんな循環が発生するのかを想像することが、これからの社会にとって必要だと思います。
みんな、なにかしら迷惑かけて生きてるじゃん
また最初に戻ります。ずっと私は「障害者である私だけなにもできない」と思っていましたし、人にできないことを頼んだり、自分が抱えている悩みや問題を肩代わりしてもらうことは、すべて悪いことだと思っていました。しかし、実は、周りの人の方がたくさん迷惑をかけていることをしている、というよりも、「いろいろ失敗しながら試行錯誤している」ということがわかってきたのです。
先ほどお話ししたように、許可をもらわなければ普通の小学校に通えなかった私は、自分の存在を取り戻そうと勉強を一生懸命行いました。失敗はできないと思っていました。もちろん勉強をすることも、何事にも一生懸命行うことも、それ自体はいいことだと思います。 しかし、一度失敗してしまうと、 やっぱり普通のところではできないと思われてしまったり、 周りから大変だねと言われたりしてしまうのではないかと、恐怖感がありました。
周りを見渡してみると、そこまで、いろいろなことに深刻になって生きている人ってどれほどいるんだろうと、大人になってみて改めて気がつきました。たとえば、 子どものときなんて、 勉強よりも漫画を読んだりゲームをしたりするほうがいいし、先生や親に内緒で友だち同士で危険な遊びをしたり、いつまでもダラダラと話をして1日が終わったりします。 そんなことをしても、ときどき怒られるかもしれませんが、自分の今後の人生が終わってしまうということまでは思わないはずです。
大人になってからできた友人の中に、お酒を飲み過ぎて、記憶がない状態で自分の部屋に戻ってきたときには、玄関でずっと寝ていたと言っていた人もいました。そんな話を聞いて、 なんだかほっとしたような、安心した気持ちになりました。今まで、「周りの人の言うことを聞かなければ、介助してもらえないかもしれない」とか、「周りの人の監視の目が強いから、変なうわさをされるのではないか」とか、 そういった不安にさらされていたので、 世の中はそんなに厳しいのかと思っていたのです。
私自身、ヘルパーさんと300人ぐらい会っていると思うのですが、 だれ1人完ぺきな人はいなくて、それぞれいろいろな過去を持っているということも知りました。 最初は、障害者じゃない人に対して、どうして障害がないのに、料理があんまりできないんだろうとか、言葉を話すことができるのに、どうして人とうまくコミュニケーションができないだろうと疑問に思っていたのですが、 徐々に、人それぞれ得意なことも不得意なこともあるのが普通なのだということに気がついてきたんです。
むしろ、社会では、みんな同じようにできることが求められて、苦しそうにしている人もたくさんいました。障害がなければなんとかできていても、 我慢して、がんばってやっている人も少なくないことも知りました。目に見えない、社会から求められている我慢大会のようです。例えば、ものすごい残業やオーバーワークは典型的な例です。 この社会で求められている何かに縛られ、それができないと、自分はなにもできないと自信を失ったり、できていない相手を責めたりしている現象があります。
その現象を止めるには、発想を変えるしかないと思います。「失敗をしたとしても、なんとかいろいろな方法でできるというアイディア」や、「自分でできないことをできる人にやってもらって、そこで節約できたエネルギーを違うところに使おう」という発想です。そういった発想ができるようになると、社会から求められている我慢大会から抜けることができるのだと私は強く思っています。
だから、迷惑をかけてもいいじゃないか。
できる人にやってもらったらいいじゃないか。
「手伝ってもらうこと」は、それだけのことではない。
そこから、他の何かが生まれるのだ。