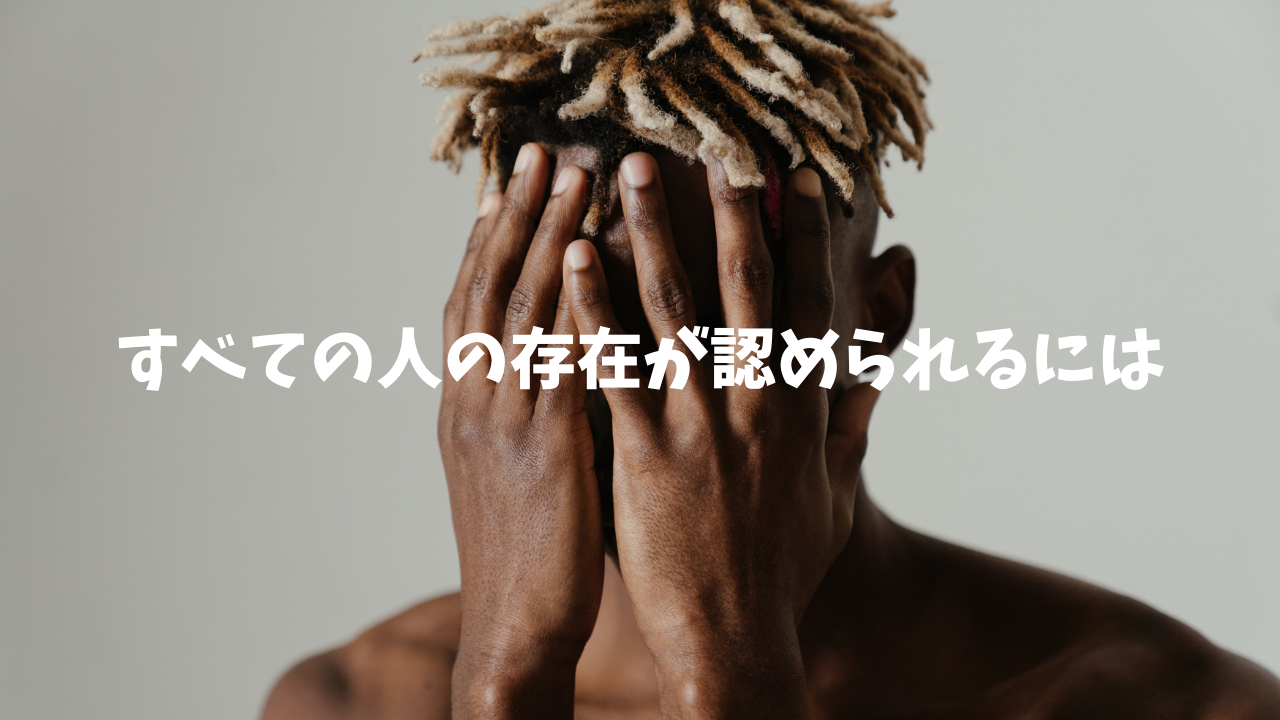私はここで生きている。みんな、自分の名前があって、いろいろな経験の中でいろいろな人々と出会い、今を生きて、これからを生きようとしている。私なら、Noboriguchi Michikoという名前を持つ人物が、その人らしく生きるために経験を更新していく。
しかし、それは、社会のありかたしだいで、有無を言わさずできなくなってしまう。
先日、自治体で行っていた「人権問題講演会」に行った。今回のテーマは、「不可視化された人びと〜その存在を認めるのは誰か」である。その「不可視化された人びと」というのは、外国から来た人びとのうち、非正規滞在者(在留資格の期限が切れてからも滞在している人)、移民・難民、さまざまな越境者たち(自国での迫害から逃れるため、家族の貧困を救うために稼いだり技術をつけたりするため、戦時中・戦後の日本による占領を受けてきたために来日してきた人びとなど)のことだ。
目次/Contents
講演会での話のまとめ
今回は、近畿大学・人権問題研究所の瀬戸徐(せとそ)英里奈教授がお話しされていた。そのお話の内容を私の視点になってしまうが、まとめてみたい。
講師は日本人と韓国人の両親から生まれ、家族を含めた自身の存在を考え続けてこられた。なぜなら、自分のルーツとつながるかどうかは国家の政策のあり方で左右されてしまうことを目の当たりにしているからだ。80年代に来日してきた外国人をニューカマーと呼ぶような時代、28歳で渡日した韓国籍の母親は、自身の名前を名乗ることができなかった。そういう母の状況を子どもの頃から見ていた講師は、自身がようやく大学生になってから、留学生でもないのに民族名・出身国の名前で名乗る在日朝鮮人と出会い、それからは母親の「徐(そ)」という名前を入れて、存在を不可視化しようとする社会の圧力をはねのけようと活動されてきた。
「不可視化」というのは、「いてはいけない」「いない」存在として扱われること。さらに、世の中には「国家から、『いてはいけない』と言われている人びと」がいるということを知っておかないといけない。
では、住民という目線で見たときはどうだろう。講師は、子どもの頃に、零細な工場地域の被差別部落(歴史的に低い生活水準や地位を負わされ、経済的・社会的な差別を受けてきた人びとが多く住んでいる地域)で、チマチョゴリを着ていた朝鮮学校の学生とよくすれ違っていた。講師は、そのような人を目にしてきたという記憶があるだけでは、知っていることにはならないと言う。どうしてそこに至ったのか知らない。認知しているが、可視化されたとは言えないということがわかったと言う。
日本は移民を受け入れている社会なのか。2019年4月に在留資格「特定技能」が新たに設置された。では、子供の頃に見てきた「働いていた在日朝鮮人の存在」は認められていなかったということか。ちなみに、日本では、ベトナムからのボートピープル(自国での迫害や困窮から逃れるために船で逃げてきた人びと)の発生が90年代まで続いていた時代、140万人もいたが、1979年から2005年までの間に日本では1万人も満たない受け入れだった。
異なる存在とすれ違うだけではいけないのだ。グットマンという人は、「日常の中で謙虚に、自分が知っていることが全てではないと思い続ける必要がある」と考えてきた。自分が持っている知識に過信してはいけない。
私たちが考えなくてはならなくなった時は、人の存在が脅かされるような非常に厳しい状況に接した時だ。その1つが2021年に1人のスリランカ女性が入管(入国管理局)の収容施設で亡くなった事件だ。交際相手からのDVにより、日本語学校に行くことができなくなり、在留資格が切れて、DVで困っているにも関わらず、在留資格が無くなったためにDVシェルターには入れなかった。DVシェルターであれば交際相手に住居を知られずに住んだのだが、交際相手の監視から逃れず、手紙で脅されて、帰国希望を出せないでいた。入管には帰国を強制され続ける中で病を患い、医療放置により死亡されたという痛ましい事件である。
東京日本入国管理センターの収容者のうち、難民申請を出しているものは3分の2。不許可になった場合に、本来その施設は、帰国の準備が整うまでにいる待合室のような場所として機能するはずである。しかし、日常生活のルールが厳しく、人間らしい生活からは遠い制限がある。中には、強制送還者を受け入れていない国もあり、ナイジェリアがその1つで、2019年に収容され続けたナイジェリア人男性が餓死で亡くなられた。
日本で景気が後退し、93年頃から日系人や技能実習生らの合法的な受け入れが始まってから、80年代からすでに来日していた人は、超過滞在労働者として扱われるようになり、入管による強制送還(自分の国へ帰りなさいと命令)をされるようになった。
さらに、入国管理局長から収容所長に、「2020年の東京オリンピックまでに不法滞在者等『日本に不安を与える外国人』の効果的な排除に取り組むこと」との通知を発表するなど、「犯罪者予備軍」に仕立てるような動きをしていったと言う。
そもそも、オーバーステイ(在留資格の期限が切れてからの滞在)に対して、入管で長期間拘束されるほど厳格である必要があるのか。
講師は疑問を会場に投げかけた。
自分が今まで考えてきたことに反省する
講師のお話を聞いて、最初に、「私もわかっているつもりになったり、わかっていないのに好き勝手に発言してたな」と反省した。講演のあと、すぐに、近所で空き缶を集めるおじいさんの姿を思い出したのだ。そのおじいさんは、決まって空き缶のごみ収集日には、空き缶がぎっしり入った大きな袋を自転車の左右前後に結びつけて回っている。アパートやマンションの外にあるごみ収集の山から、手で空き缶を取り出して、自分の袋に入れていた。私は、そのような人びとを北海道の札幌で見かけたことがなかったので、珍しい人として「おもしろいな」と感じていた。大きな荷物とともに自転車を漕ぐ後ろ姿に、生きているエネルギーといったものを感じたし、札幌のときのように「見えない存在」ではないということに新鮮さを感じたのかもしれない。
しかし、それだけで、おじいさんがなぜ空き缶を集めているのか?という「存在の深掘り」まではしてこなかった。もしかしたら、生活費をまかなうことができずに空き缶を集めて売ることで生きているのかもしれない、国の制度で救済されずに自分でやるしかない状況なのかもしれない、国の制度を使っていたけれどぞんざいな扱いをされてきたのかもしれない…。インターネットの記事で調べてみると、生活保護の申請は会社に就労しようとすることが申請であったり、生活保護の受給をしたとたん、いろいろな縛りがあるため、自分で働く手段として空き缶収集をしている方もいるようだ。もちろん、まだまだ知らないことだらけだ。私は、おじいさんを風景でしか見ていなかった。反省だ。
また、外国人に対しても、日本で外国人を見かけることが多くなったからといって、理解をしているとは限らない。私は、日本語教師をしたり、日本語教室のボランティアに行ったりすることがあるが、そこでも差別的な発言をまったくしていないという自信はない。どうしても、日本語の初心者の方は片言でしか話せないので、ネイティブである日本人の力が大きくなってしまう。そのために、日本人側が外国人を子ども扱いしたり、少し日本語が話せたくらいで大げさにほめてしまい、相手の経験を度外視して下に見た態度をとってしまう。私もそういったことを何回かしているので、自分の無意識にある何かを取り除きたい気持ちでいっぱいだ。
収容施設での非人道的な扱いに怒りが起こる
東日本入国管理センターでは、316人の人々が収容されているという。そこでの生活では、自由時間が午前午後と2時間程度しかなかったり、運動時間はたったの40分、その時間以外は6畳で5名が過ごしているそうだ。窓には黒いシールで外が見えないようになっており、外出は禁止され、面会時間も日中のうち一人につき30分しか認められていない。病気になってもすぐには治療は受けられず、先ほどのスリランカの女性やナイジェリアの男性の死も、劣悪な環境の中で至ってしまったことだと言われている。
私は、日本で歴史的に、障害者が収容され続けてきたのと同じように、現在も「異質」とみなされてしまう人びとへの「非人道的な扱い」が法律で容認されていることに憤りを感じた。しかも、そういった扱いをされるような犯罪をしたわけでもないのに。全国で入管の施設で収容されている人びとは、およそ1200人、そのうち医療がすぐに受けられず死亡したのは2007年以降、17人だと言われている。それが少ないと言えるのか。
不信感しか生まない方向性に気づくべき
「日本に不安を与える」人を排除するという思考の方向が恐ろしくて仕方がない。私は、入所施設で暮らしていたときに、集団でプライバシーもない状態で毎日を過ごし、外出もできず、起床や就寝の時間までも決まっていた生活だった。そこでは、気持ちが前向きになることは一切ないし、それどころか職員との上下関係を生み、服従するしかない状況だった。そんな状況では、外出したいとか、仕事をしたいといった希望を持つことはできず、衣食住が満たされていることにだけ感謝して、気持ちを抑えるしかなかった。
入管の収容施設では、人間扱いをされず、さらに外出や施設から退所できる目処も知らされない。そんな状況下で、人はどんどん不安になっていくだけだし、人に対する不信感が増幅する一方だと思う。もし、気狂い(きちがい)を起こしている収容者の映像をニュースで流してしまったら、何も知らない日本人は怖いと思い、さらに、「存在の深掘り」をすることを避けるだろう。
強いインパクトでわかったつもりになってはダメだ。もっと、きちんと事実を知ることが必要だと思った。
すべての人の存在が認められるには
私は、このテーマで書こうとしてから、少し時間がかかってしまった。聞いた情報に衝撃を受ければ受けるほど、それをどう消化したらいいのか、答えが見つかるまでに時間がかかってしまう。多くの人は、私も含めて、複雑なことや、嫌なことには目をそらしておきたいと思っていると思う。時間の流れで、一度衝撃を受けたことでも、頭の中から忘れていってしまう。
しかし、世の中は、いろいろな情報がいつも飛び交い、その多くはネガティブな言葉や方向を示してくると思う。本当なら、子どもでも、女性・男性でも、多様な性のあり方も、高齢者も、障害者も、外国人も、環境破壊により被害に遭った方々も、すべての人の存在がきちんと認められたら、生きやすい社会になっていく。
このテーマについて考えるのはしんどかったけれど、私はいつも「一番しんどいのは、本人」だと思うようにしている。本当に小さな行動だから、やれることだ。
私は、小さな負の連鎖も生まないようにしたいし、小さな良い連鎖を起こせるようなことをしていきたい。そのため、まったくこの状況を知らない方々にも届くように、そして、私自身が心に刻めるように、このテーマで書くことにした。
より多くの人の存在が「可視化」されて、その人の人生がどんな歴史や社会とつながっているのか、「存在の深掘り」が必要だと思った。