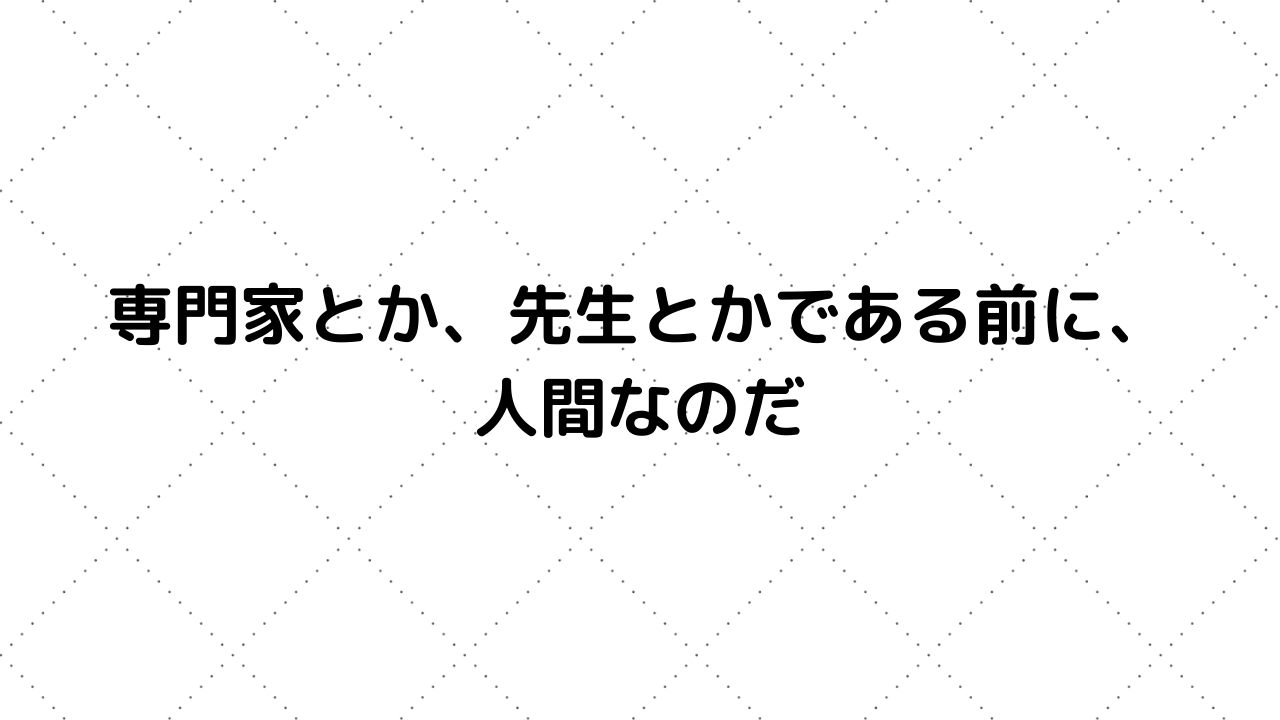最近、夢中になっていることがある。それは、今まで経験したことのない分野に挑戦していることだ。福祉とは違う専門の仕事を知ると、新しい発見が山ほど出てくる。それがとてもおもしろい。今日はそんな話をしてみたい。
私は、今、日本語教師を目指して養成講座に通い、資格を取り、仕事をしようと考えている。始めてから半年くらいしか経っていないが、日本語教師の資格をすぐに取れる道として、1ヶ月後にある全国の日本語教師の試験を受けるつもりだ。実は、試験を受けずに、養成講座に通っているだけでも、それが終わるのと同時に、日本語教師として就職できる条件を手に入れることができる。ただ、早く資格を取って、就職したり、フリーランスで働いたりしていきたいと思っているため、養成講座の課題をこなしながら、試験勉強をしている。(ブログの更新が遅れているのは、そのせいです。。。)
日本語教師を選んだ理由はいろいろあって、また今度のブログで書いていきたい。今、大きく感じていることは、「この仕事を続けてみたい」というワクワク感だ。福祉の分野とはまったく違う世界だが、勉強していくうちに、私のこれまでの経験がまるごと活かせそうということがわかったからだ。さらに、「弱い人を救う福祉」と特別視していたことが、やっぱり「もっと身近で、だれにでも必要な福祉」と考えるべきだと改めて思ったのも、日本語教師の勉強をしてからだ。
日本語教師は、主に外国人や日本語に触れる機会が少なかった日本人で、何かの必要性があって学ぼうとしている人々に、「日本語の組み立て方」を教える先生である。生まれてから日本語に触れて話せるようになった人々は、「日本語の組み立て方」は子どもの頃から知っているので、学校に入学してからは「日本語の仕組み」を勉強する。料理でいうと、「この材料とこの材料を、この調味料で組み合わせて焼いてみる」というのが「組み立て方」で、「できた料理をバラバラにして、材料や調味料の種類、どのくらい焼いているかなどを細かくみる」のが「仕組み」だ。
生活をしていくためには、どちらを先に勉強する必要があるだろうか。そう、「日本語の組み立て方」である。「仕組み」ばかりを見ていても、誰かに道を訪ねたり、遊びに誘ったり、病院でお医者さんと話したりすることはできないのである。
「福祉」と「日本語教師」の世界で共通していることを一つ挙げるとすると、どちらも「上下関係が生まれやすい」ということだ。日本語を学ぶ相手(学習者、と呼びます)は、大人であっても、最初は、ひらがなすら読むことができない。そのため、日本語をネイティブとする人が、日本人の小学生のレベルのことを教えることになる。学習者は、年齢相応に社会経験を持っている。日本語教師は、そのことを頭に入れておかないと、子どもに相手するような言葉遣いや態度を取ってしまう。
「福祉」の分野では、まさに、専門家が、相手を子ども扱いするような態度をしてしまうことが多い。「子ども」とまでは思わなくても、「自分より社会経験がない人」と見下した態度を取りがちだ。福祉の分野の教科書には、必ず「高齢者も障害者に対して、その人らしさや人権、そして自己決定を尊重しましょう」といった内容のことが書かれている。教科書に書かれているということは、見落としてしまいがちであるということだ。
実際に、日本語教師の勉強では、「ベビートーク」「ティーチャートーク」という言葉を習う。「ベビートーク」は「〜だよね、うん。」「〜なの?」など赤ちゃんに声をかけるような話し方のことで、「ティーチャートーク」は教室で使われる「最初に覚えていく」「学習者が勉強したことのある」言葉で話す方法だ。
もう想像がつくと思うが、ベビートークは絶対にしてはいけないことだと教わる。一方で、ティーチャートークは、日本語を習っていく段階に合わせて、習ったことのある日本語で、次の新しい日本語を教えるために必要な話し方だ。しかし、これも、注意が必要と言われている。それは、教室内での日本語になってしまうため、実際の生活では、(学習者にとっては)ネイティブすぎる日本語をたくさん浴びるため、「教室での学習は特殊な空間」になってしまうからだ。学習者は、実際の生活で日本語へのエネルギーをたくさん使っていることを、教師は理解しておかないといけない。
私は、日本語教師として学習者に気をつけることと、社会福祉士として障害者や高齢者に気をつけることと、そんなに変わらないと思う。ただ、日本語教師では、教科書や先生の説明から、具体的に気をつけることや陥りやすいことを教わるが、福祉では、「尊厳を守る、自己決定を尊重する」などと抽象的すぎると思った。
もっと、「専門家は、高齢者や障害者に対して、自分より身体や認知機能が劣っていると見てしまい、子ども扱いをしてしまいがちになる。支援をするということは、生きづらいところを具体的な手段を提供することで生きやすくし、その人の生活や人生全体の循環を円滑にすることである。本人にとって「親しみ」「愛情」が必要と思ったとき、なぜ必要なのか、どんな言葉がけが必要と専門家は思ったのか、それによって本人がどうなることを(本人自身が)望んでいるのか、その対応により専門家が陥りやすい問題は何かを客観的に見ていく必要がある。」といったように、具体的に示す必要があると思う。
どうしてそのように考えるかというと、専門家はどこかのタイミングで、「専門家自身の自己受容」といった「認めてほしい、近い存在だと思われたい」という欲求と態度が混ざってしまうことがあるからである。
専門家であっても、先生であっても、人間だから、自分の醜さが出てしまうことがある。でも、仕事としてやっている以上、また、ただでさえ生活に困っている相手の支援をする以上は、専門家の欲求を満たす場にしてはいけないのである。
そして、それぞれの生き方に対して、社会的に良いか悪いかを審判する人でもない。自身の生き方も「みんなに披露できるほど、すばらしい人生なのよ!」と腕を広げて言えるだろうか。迷い、失敗し、誰かと別れ、良い人と出会い、そしてまた繰り返していくのではないだろうか。
もちろん、人に故意に傷を負わせたり、命を落としたりすることは止めるべきである。日本語教師の世界では、最初の学習段階で、「飲みます」「呼びます」と同じ動詞のグループである「死にます」という動詞を教えるかどうかで意見が分かれている。そのあと「飲んで」「呼んで」という形の変化を習い、「〜てください」というお願いの表現などを習っていくのだが、「死んでください」と日常的には使わない「違和感のある言葉」である。
言葉は、言葉を発する本人の心情にも大きく影響を与えると言われている。日本人にとっては、「死んで」は、一万語以上の言葉のうちの一つだが、学習者にとっては、日本語の組み立てを習い始めたばかりの人ほど、その一つ一つの言葉のインパクトが強い。学習者には、生活に使う言葉を優先的に習うことが普通である。そのような考えを前提にしながら、言葉をどう教えていくのかを考え続けるのである。
誰かの助けになるということは、弱い人や劣っている人を助けるのではなく、自分を知って、人との付き合いを模索していくことなのだと思う。
まったく違う分野の世界に入ると、さらに、自分が関わっている領域の奥深さを感じた。どこに進んでいようとも、自分の「何か」につながっているんだと思った。