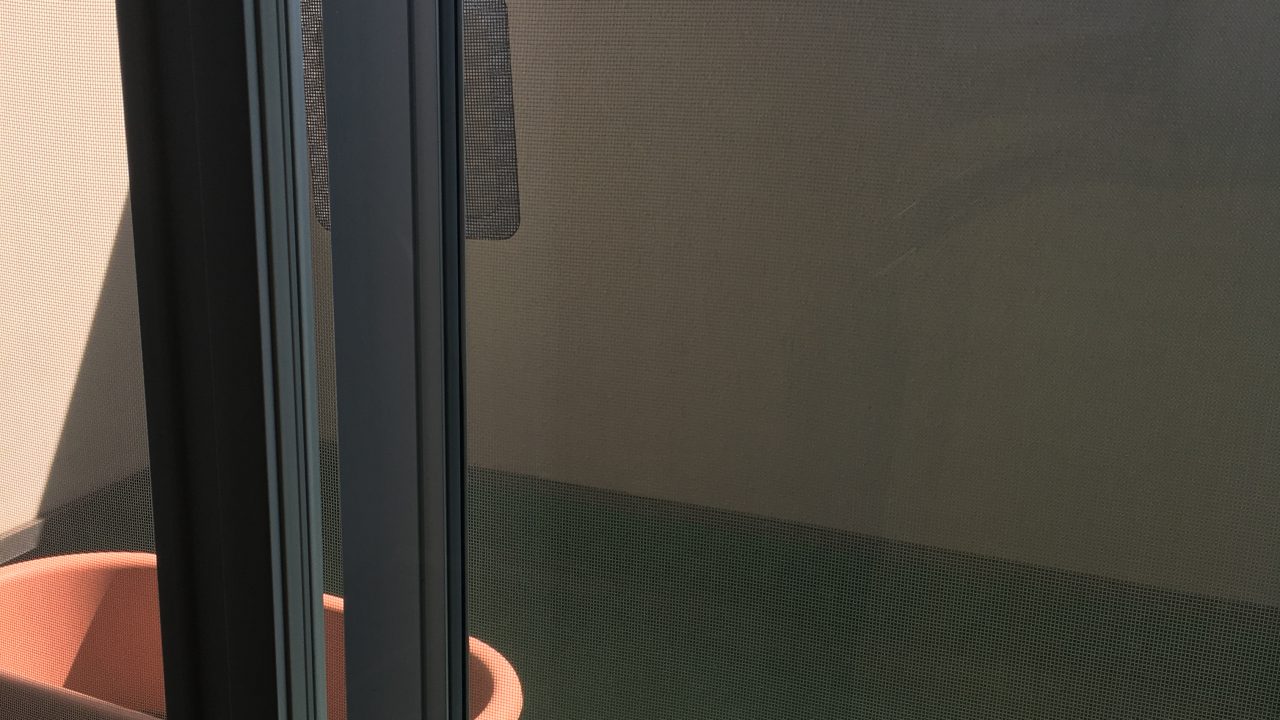最近、色々なメディアで色々な人々が「コロナに負けるな」「みんなで頑張ろう」という言葉を使っているのを耳にします。そのような言葉を聞くと、災害時のことを思い出し、その時もそうでしたが、何かの違和感を感じて仕方がありません。「どんな時でも頑張らないといけない」「負けてはならない」という緊張感と対抗心が、その言葉の背後にあるような気がするからです。
その言葉の背景まで考えると、複雑でどこまでも想像してドツボにハマりそうです。なので、やっぱり「自分の生活を正直に見つめ直すこと」で、私たちはこの状況でどう考えていけば、安心して暮らしていけるのかを考えていきたいと思います。
目次/Contents
今回は、「これから、私たちはどんな心構えを持つことが大切なのか?」を考えてみようと思います。

北海道も夏がやってきました。窓を全開にして、鳥のさえずりや、どこかの工事の音、近所の生活音などを聞きながら、爽やかな空気を自宅に送り込みます。エアコン無しには居られない本州と比べて、北海道ならではの夏の過ごし方かもしれませんね。
社会全体が、少しずつ、通常の生活に戻ってきたように思います。時間差で登下校する子どもたちの賑やかな声、再開した工事の音、飲食店から漂う美味しい匂い、会社に向かうサラリーマンの通勤ラッシュの空気…そのような刺激を懐かしく思うほど、以前は静寂の中にいたようですね。
今回は、「これから、私たちはどんな心構えを持つことが大切なのか?」を考えてみようと思います。「私たちは」と書きましたが、それぞれの状況や生活スタイルによって違うと思うので、あくまでも「私は」という感じで書いてみますので、皆さんも心構えを考えるきっかけにしてもらえると嬉しいです。
皆さんは、これまで、どんな気持ちの変化がありましたか?
新型コロナウィルスがどうやら発症したらしいという情報を知ってから、私たちの生活を脅かしているという現実を目の当たりにするまでに、様々な気持ちの変化があったと思います。
きっと、これからも変化する可能性があります。それを、ちょっと予想してみて、それに備えていくという意識でいると、また混乱したり、ストレスが過剰に溜まったりすることを避けられるような気がしています。
私たちは「常に、過去や歴史から、学ぶ」と言われるように、まずは、今までのことを振り返ってみましょう。
遠くのこととして認識していたころ
〜クルーズ船での発症や数人の発症
あくまでも、クルーズ船にいた方々は現実ごととして経験されていたことは言うまでもありません。もし、家族や友人がそこにいたなら、自分はそこにいなくても、現実的なこととして心配していたことでしょう。そこにいなかった私は、ラジオなどのニュースで聞く程度で、まだ旅行の計画を実行していた時でした。
- 危機感はまったくなかった
- 遠いところでの話という認識だった
- 自分の生活が変わってしまうということは思いもしなかった
- 意識は少し傾けていた
北海道で第一波が発生
〜どうして北海道が?という驚きと不安
2月は、北海道の感染者が急激に増えました。北海道知事が国より先に、緊急事態宣言を出していたことが、事の大きさを示しています。関西の知り合いの方からすぐにマスクを送ってくださいました。大勢の密度を避けるよう、ライブやイベントはこの時期からキャンセルが相次ぎます。
私は、雪が積もっている時期だったために、もともと外に出られなかったので、おそらく人よりは危機を感じていなかったと思います。でも、ヘルパーさんが代わる代わる来るので、ヘルパーさんを守ることが優先だと思いました。
- 自分の健康よりも、ヘルパー同士の感染を防ぐことを一番に考えた
- でも、ヘルパーさんの意識もバラバラなので、どのように対策を統一したらいいのか、全くわからなかった
- ヘルパーさんの不安も聞くことが多くなった
- 考えるほど、情報が少なすぎて、インターネットで探す時間が長くなった
- 札幌の感染者が増えたことで、不安が襲って来た
- 催し物などのキャンセルが多くなり、がっかりする声をたくさん聞くようになる
- 落ち込んでいる人にかける言葉が見つからない
- 自分も本当は不安だが、人の話を聞くうちに、自分の気持ちはどこかに行ってしまい、不安なことも言わなくなる
- 外に出ると神経を使うので、3週間以上、一歩も出ない
日本全国で緊急事態宣言
〜そんな中、また北海道で第二波
北海道の最初の自粛期間が終わって、また何週間か後に第二波が来ました。そんな中、徐々に日本中で感染者が出るようになり、国もようやく緊急事態宣言を出します。コンビニやスーパー、病院などの必要最低限の場所以外は、ほとんど休業し、街は一気に静まり返りました。小中高等学校や、専門学校や大学なども、もうすでに新学期が始まっているはずだったのに、難しくなってしまい、卒業式・入学式・学生の歓迎式などは全てキャンセル。甲子園やオリンピックなども、延期などの判断がくだされました。
- 第一波で緊張していたため、そろそろ疲れてきた
- ニュースやSNSでは悲しい情報や、感染者数の数字を見るたびに、心が苦しくなる
- 自分の身近に感染者がでてしまったらどうしよう?ということばかりを考える
- コロナを連想させる情報はなるべくシャットアウトする
- 一方で、マスクをしていない人やで歩いて遊んでいるような人を見ると、「私は家にいるのに、密を作ったらダメじゃん」と苛立つ人も出てきた
- なお、外出を警戒して、自宅で過ごすことを続ける
- この生活がいつまで続くのかわからないまま、ひたすら自分に良いことだけをやる(あとで記述します。)
緊急事態宣言により、仕事がなくなったり、生活が苦しくなったりした人々が増え始め、街にいる人々を少し怖く感じる
街に人々の気配が少なくなったのと同時に、お酒を昼間から飲んでいる人などが目立ってきたとヘルパーさんが行っていた。夜に一人で出歩くのも怖いという声もあり、全然気にしないヘルパーさんもいたが、ヘルパーを派遣している身としては考えないといけないと思った。
- 街全体が暗くなっていると感じる
- 自分の身は自分で守らないと!という意識が高くなる
- 家族や友人と無性に連絡を取りたくなってくる
- これは長期間の戦いになりそうだと覚悟を決めるようになる
緊急事態宣言が解除されて、ビジネスが戻ってきた今
宣言が解除されたことにより、スーパーに行くことや散歩に出かけることなど、少しの用事なら出ていこうという気になってきました。いつも通っていた飲食店を応援しようとテイクアウトを取り始めたりするものの、店内で食べることはまだしたくない。今は、誰もが気持ちを緩めやすい時期になってきたので、気をつけていかなければと思っています。
- オンラインでの家族や友人との連絡にも慣れてくる
- オンラインのイベントに参加し始め、人との交流を少しずつ増やす
- 自分の仕事について方向性を決め始める
- 自分の生活についても方向性を決めていく
- 気を緩めた後に、何か大きな波が来ないかと、内心は緊張している
今までの生活が当たり前だったからこそ、ショックは大きかった
新型コロナウィルスによって、世界中で状況が変わってしまいました。今までの生活が当たり前だったからこそ、ショックは大きく、その心情の出し方に困りました。
まずは、これ以上の被害を食い止めないといけないということだけを考えていた日々を送っていましたが、感染対策や予防対策を公的に保障してもらわなければ、個人でできることは限られていました。
自分が深刻になればなるほど、他人の行動が気になり、「もっと気をつけてほしい」と思うこともしばしば。その人にとっては、神経質にならないでいることも、その人なりの気持ちのバランスの取り方だったのかもしれません。
でも、感染したり、感染させたりしたら、元もこうもない。「手洗いを徹底、消毒もすべて行う、距離は離れて」というスタイルに慣れるしかないと、言い聞かせていました。
見えない出口にいるとき、今いるところで、自分に良いことをするしかない
生活の9割は、感染症の心配で埋め尽くされていたのですが、後の1割は自分に良いことしかしませんでした。
申し訳ないけれど、ヘルパーさんの話は、意識の中の半分で聞いていて、友人とも音信不通でいた時期が長かったです。
その間、やっていたことは
- 「自分の食べたい好きなものを作る」
- 「自分が今集中している勉強をやり続ける」
- 「自分がこれからお金を稼ぐ方法を考える」
- 「自分の将来の生活を思い描く」 ことに集中していたのです。
きっと、もっと、友人同士で助け合ったり、コロナに関して支援が不十分な福祉の現場を訴えたりすることはできたかもしれませんが、私はそれ以上のキャパシティがないことを自覚していました。
今、目の前にいる、家族やヘルパーさんとの関わりを大切にできるくらいの気持ちの余裕を持つことに決めていました。
そういった、自分の限界を知って、自分やその近しい人にどういう関わりをしたいかをわかっていると、自然と、今やるべきことが見えて、迷いが全くなかったのです。その行動は、私にとって正解でした。
「見えない、考えたことがないこと」にどう向き合っていくかが大切
「コロナに負けるな」という言葉が飛び交っていますが、じゃあ、どうしたらいいのだろう?と思うことがあります。「コロナと戦う」という表現の裏には何があるのでしょう。
これまでの「私の変化」を見ていくと、「見えない、考えたことのないこと」への耐性ができていなかったことが大きく関係している気がしてなりません。
メディアによって、私たちは、感染者数や死者のこと、「3密を避けろ」「緊急事態宣言」などの言葉を、いやというほど聞いてきました。でも、この先どうなるのかわからないという不安ばかりを掻き立て、どういう心づもりでいけばいいのか、自分たちで考えるしかありませんでした。
社会全体で、その不安が自分や誰かを攻撃する引き金となり、ストレスがまたストレスを呼ぶ日々が続いていました。きっと、私たちは、どこに向かっていくかという方向性がなければ、生きていけない生き物なのでしょうか。その的が欲しいのでしょうか。
私は、結論を言うと「コロナに負けるな」「コロナと戦え」と聞くと、見えない状況の中で、なんとか的を決めたような錯覚に陥るのです。
大切なのは、コロナに限らずとも、「見えないこと、考えたことがないこと」への向き合い方を考えることなのではないかと思います。
そのポイントを私なりに考えてみました。
「見えないこと、考えたことがないこと」への向き合い方
- 「見えない」ことの不安をノートに書き出して、可視化する
- 「何が見えてほしいのか」を不安の下に書いて、可視化する
- 「見えてきたら、何をしたいと思っているのか」を書いて、可視化する
- 「考えたことがないこと」について書き出して、可視化する
- 「考えたことがないこと」の中で、取り組んだ方が良い順に優先順位をつける
- 優先順位の順番でやってみる
- わからなかったら、家族や友人、同じように考えている人をインターネットで探してみる
- 情報や助っ人を探すのに疲れたら、食べたいものを食べるか、寝る
食べたいものを食べて、寝たい時に寝るたびに、不思議とパワーが戻っていました。どんなことがあろうとも、食べて、寝ることは大事なんだということに気がつきました。
新型コロナウィルスによる
「障害」をどう乗り越えていくか
〜できないことではなく、
できることに焦点を当てて
障害者として生きてきた人々は、普通の生活をしようとすると、いつも「障害」にぶつかってきました。そのため、「できないことではなく、できることに焦点を当て、どうやったらできるようになるかを、個人だけでなく、社会全体で工夫することが必要」であることを知っているのです。
コロナウィルスで「何も考えず、外に出て遊んでいる人を見ると苛立つ」のは、「自分も我慢しているのに」というストレスと、「感染リスクを下げたい」という安心安全を求めているために起こる反応です。
しかし、障害者は、「健常者を見ると苛立つ」ことをしても意味がないことを、身をもって知っています。問題はそこではないからです。
それと、「コロナ下の中で、頑張ろう!」というのも、違和感を感じています。障害者は、「どんな体の状況でも人間として生活できる社会を目指し、人が社会に合わせて苦悩の中で我慢するのではなく、環境や社会を人々に合わせて生きやすくしていこう」と言ってきました。
そのため、「コロナの中でも頑張ろう」ではなく、「生きやすい社会にしていこう!」で良いと思うのです。もちろん、コロナ対策を考えることも含んでいますが、それ以外にも生きづらいと感じることが表に出てきたはず。
これをきっかけに、社会の生きづらさを抜本的に改善していこう。
私は、それに尽きると思います。
頑張るのではなく、生きやすいように、社会の仕組みを修理していこう。
皆さんも、これまでの気持ちの変化と、これからに備えた振り返りをしてみませんか。