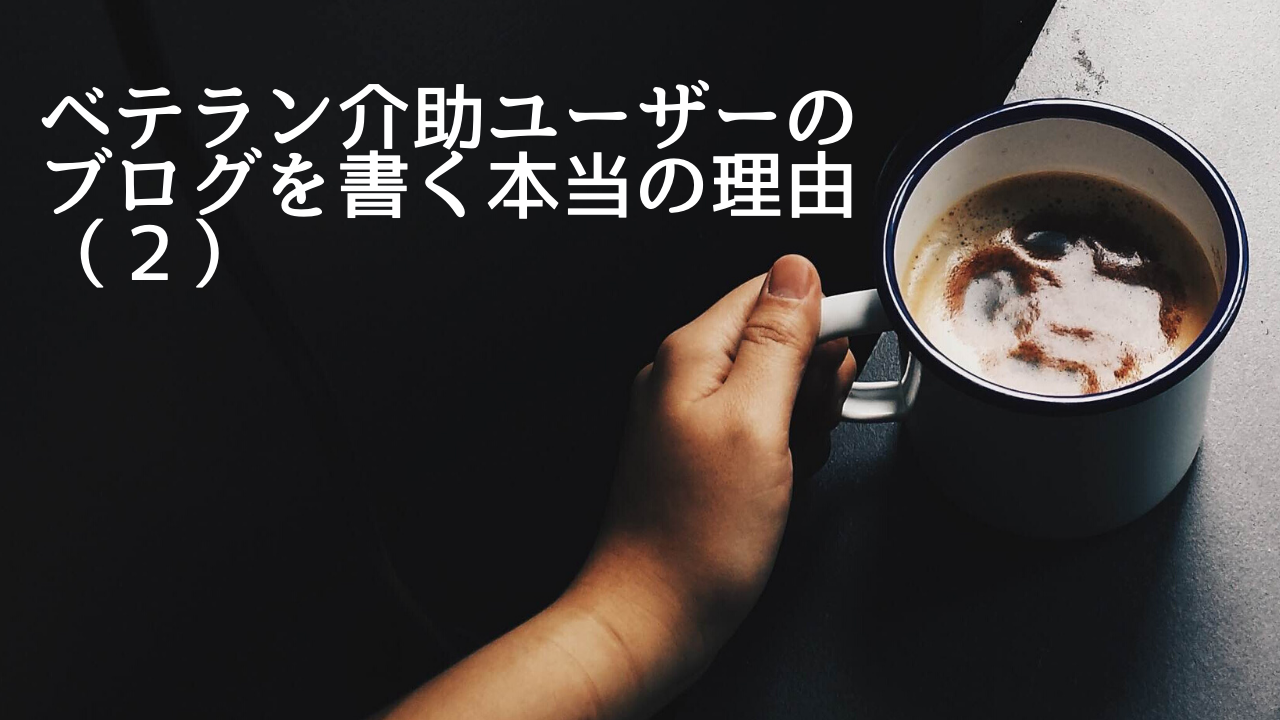前回の「ベテラン介助ユーザーのブログを書く本当の理由」では、ホームヘルパーを利用しながら、自分の生活を送ろうとしている人の話は、どんな人でもこれから体が動きづらくなってくることや、何かのタイミングで怪我をしてしまうことがあるので、みなさんにとって、とても大事な話です、ということを書いた。
「自分の生活を送る」ということは、「家族でも、他人でもなく、自分が続けていきたいと思うような生活をする」ということ。私は、その生活をするために、オシッコやウンチ、水を飲む、着替えるなどの手助けをするホームヘルパーを利用している。「自分らしい生活をする」ために、「他人の手を介して生きる」という、どちらかが強すぎると、どちらかが弱まってしまいがちな生活だ。
そのような生活を生まれたときからしている私は、ベテランだと思ってもいいと思う。しかし、そのベテランの意味は、失敗なく、不自由なくヘルパーさんを使いこなすという意味ではない。「ヘルパーさんを利用しながら、自分らしい生活をそのまま続けることは、かなりレベルの高いこと」だということを知っているという意味で、ベテランだ。
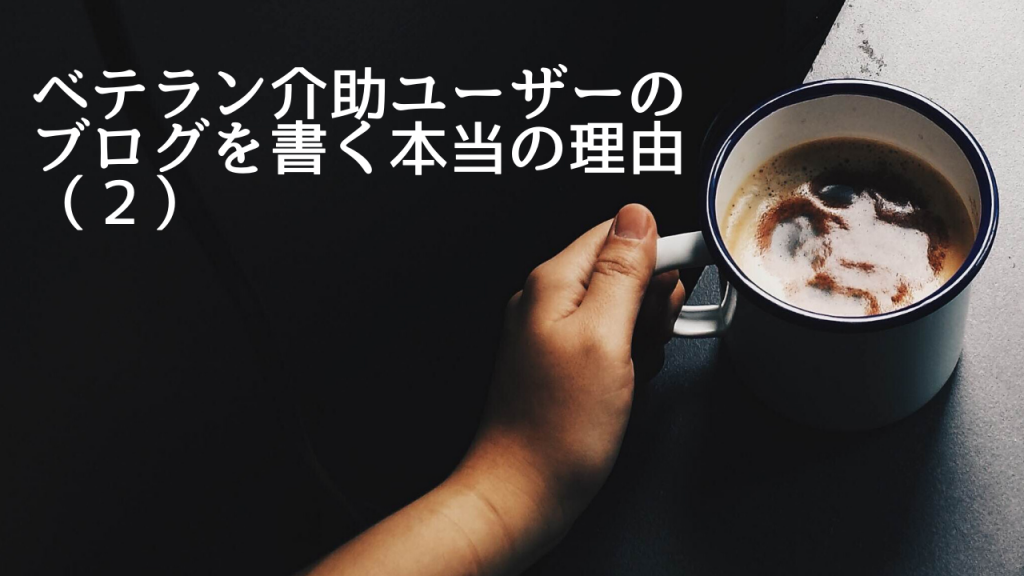
その難しさはどこから来ているかというと、お互いに持っている頑固な考え方によるものだと、私は思っている。ヘルパーができるほどの体の機能がある健常者は、子どもの頃に、障がい者と友人として関わったことのない人が多いために、障がい者と聞いただけで構えてしまう。ヘルパーの介助が必要な障がい者は、健常者に対して「なんでもできる人」「気持ちをわかっているはずの人」「障がい者の気持ちなんてわからない人」だと思っている人が多い。(そういう人ばかりではないが、そういう気持ちになりやすいという意味で「多い」ということです。)
高齢者になって体が動きづらくなってきた人に対して、その人よりも動ける人は、「こんなふうになりたくないな」「惨めだな」と思う人も多い。私なら、さぞかし(→ふだん、さぞかしって使わない(笑))「体が辛いが辛いだろうな〜」と思うことはあっても、惨めだとは思わない。
妊婦さんに対して、「私だって疲れている」と電車などの優先席を譲ろうとしない人もいる。ベビーカーごと電車に乗ったら、周りには邪魔だと思う人もいる。妊婦さんやベビーカーを押している家族側が「すみません」と肩身狭い思いで、外に出てしまっている。高齢者に電車の席を譲ろうとしたら「そんな歳ではない」と怒る。周りはそれが怖くて、断られたら恥ずかしいので、声をかけることさえもどんどんしなくなり、電車の中だけのことを考えても、「いや〜な循環の空気」が広がっていく。
このように、お互いの「いや〜な循環の空気」を生み出す思考は、どの分野にいる人にも広がっているので、そんな空気のことに気づいていないヘルパーが来ることの方が多い。そもそも、どんな人でも弱いところがあって、そこを誰かに助けてもらっている。その中でも、おしっこやウンチなどの生きるために必要なことに手を貸す人が、主にヘルパーなのである。特別なことではないのだ。
だから、みなさんの生きづらさは、めぐりめぐって、誰かの生きづらさにつながっている。そのあたりのことを、生きやすくなるように思いをめぐらせてみようと思った。
そんなことをこれからも発信していきたいと思う。