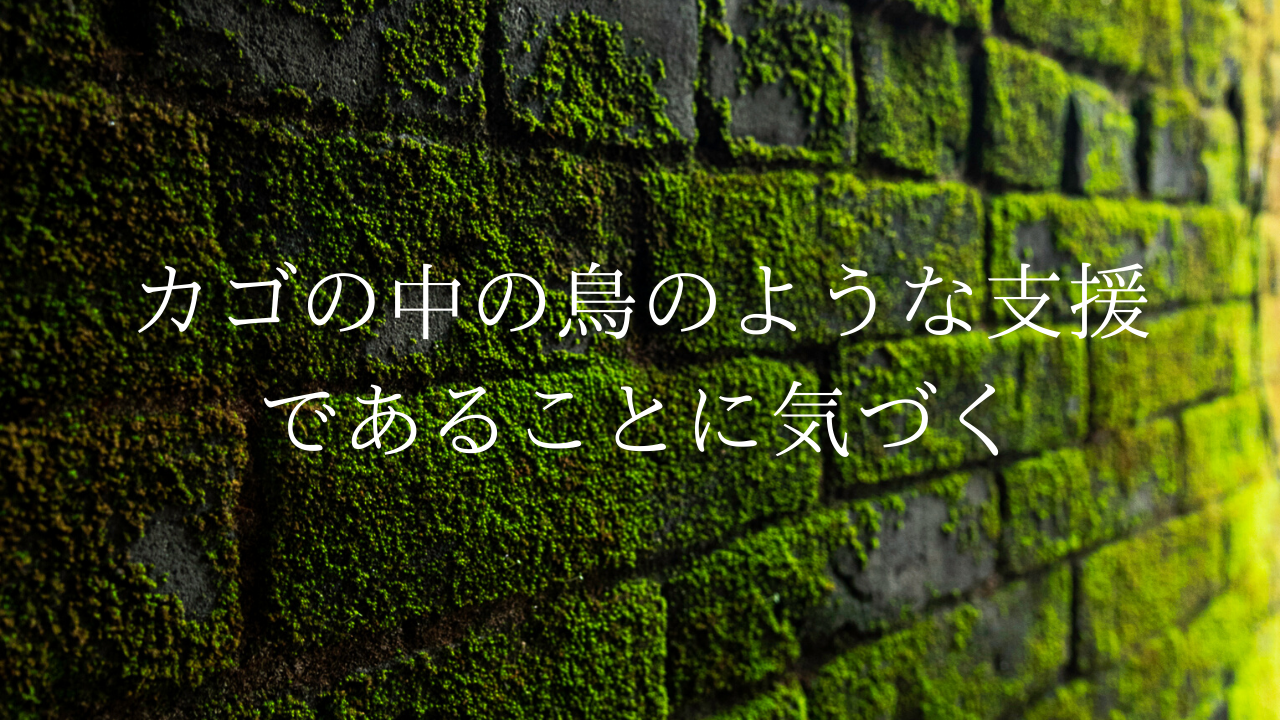「障がい」とはなにか 第6回
「障がい」とはなにか 第6回
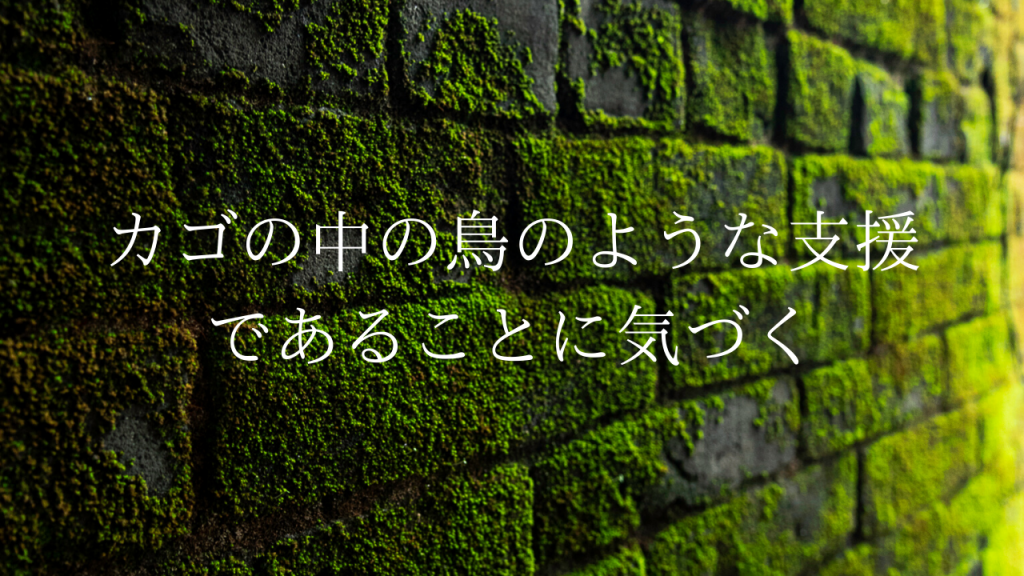
「動けないことはこういうことか…」―思春期にかけて、自分は「障がい者」なんだと思い知らされた。
10代の頃の生活場所だった病院や寄宿舎では、「何かあった場合の責任がある」ので何日も前に届け出をしないと外出ができなかった。子どもにとっては、歩けない、トイレに自分で行けないことよりも、冒険したり、挑戦したりする機会を失っていることの方が大ショックである。
周りの大人の職員に、常に見守られ、お尻を拭いてもらって「お世話になっている私」。高校の時、朝起きたあとに野菜ジュースを飲みたくて寄宿舎の先生にコップに入れてもらっただけで、「忙しい時間にやめてほしい、もう他の職員にも頼まないで」と言われた。毎朝ウンチをするのに急かされてしまうので飲みたかったのに、野菜ジュースくらい飲まなくても死なないと言い聞かせて言葉を飲み込んた。今だったら、職員が空いている時間に、蓋付きのコップに移しておき、飲みたい時に自分で冷蔵庫から出せばいいと思いつく。しかし、経験がない高校生の私には成すすべもなかった。
「生きていくうちに、障がい者になっていった」という表現が正しいかも知れない。生まれてから高校生までは何度も思ってきた。普通の高校生の生活を知らず、寄宿舎の建物の中でひたすらもがいていたのであった。卒業後はまた母親に苦労をかけるのか、施設で同じような生活を送るのか、どこで生きていけるのかわらないまま、進路を決めなくてはならない地獄。まるでかごの中にいる鳥だった。
前回の記事で、私の手を可愛らしさで見てくれる経験をしたという話をした。それ以前は、自分の体はまさしく「治療の対象」だった。5歳の頃に、股関節を脱臼していたため、骨を削る手術をした。足に巻いたギブスを数日後に電動のこぎりで切ったときは、足も切れるんじゃないかと息を止めていた。小学生の時はわざわざ授業を休んでリハビリに通い、中学生の時は病院で生活しながら、そこに併設された養護学校で授業の一環としてリハビリを行っていた。年に1、2回は、お医者さんに、私の腕や足首の角度をコンパスで測られたり、レントゲンで背骨や股関節の骨の様子を見られたりしている。まるで自分の体は人形だと思わないとやってられなかった。
これまで、おそらく500人以上の福祉や医療の支援者と出会ってきた。多ければ多いほど、考え方が合わない人も出てくる。考え方が合わない人というのは、「可能性を閉ざしてしまう人」を意味している。
たとえば、就学相談で「あなたのお子さんは普通の小学校へは行けない、養護学校に行きなさい」と言われたことがあるが、その相談員はそれが正しいと思って言っていた。
相談員のアドバイスよりも、自分の意思をつらぬいたことで、6年も普通の小学校に通っている間、車いすごと入ることのできるトイレが作られたり、校庭にスロープがついたり、階段を上る昇降機が置かれたりして、私が卒業したあとも車いすの子どもが通えるようになった。
母親が「私の子どもが普通小学校に通ったら、人様に迷惑をかけてしまう。相談員の方のアドバイスどおりにしよう」なんて思ってしまったら、私の今の人生はなかっただろう。そして、小学校もバリアフリーにはならなかったし、車いすの子どもも通えなかったかもしれない。
支援者に、いつも感謝すればいいかといったら、本当はそうではない。もちろん、やってもらったことに感謝をすることはいいことだ。しかし、支援者は、専門知識を持っていて感謝されるポジションにいるからといって、大きい存在ではないのである。そして、障がい者や高齢者、その家族は、感謝をすることが多いからといって、自分たちの存在を小さくする必要もない。逆に、大きく見せようと頑張る必要もない。
支援者も、支援を必要としている人も、カゴの中の鳥のように、狭い範囲にいるのかもしれない。(つづく)