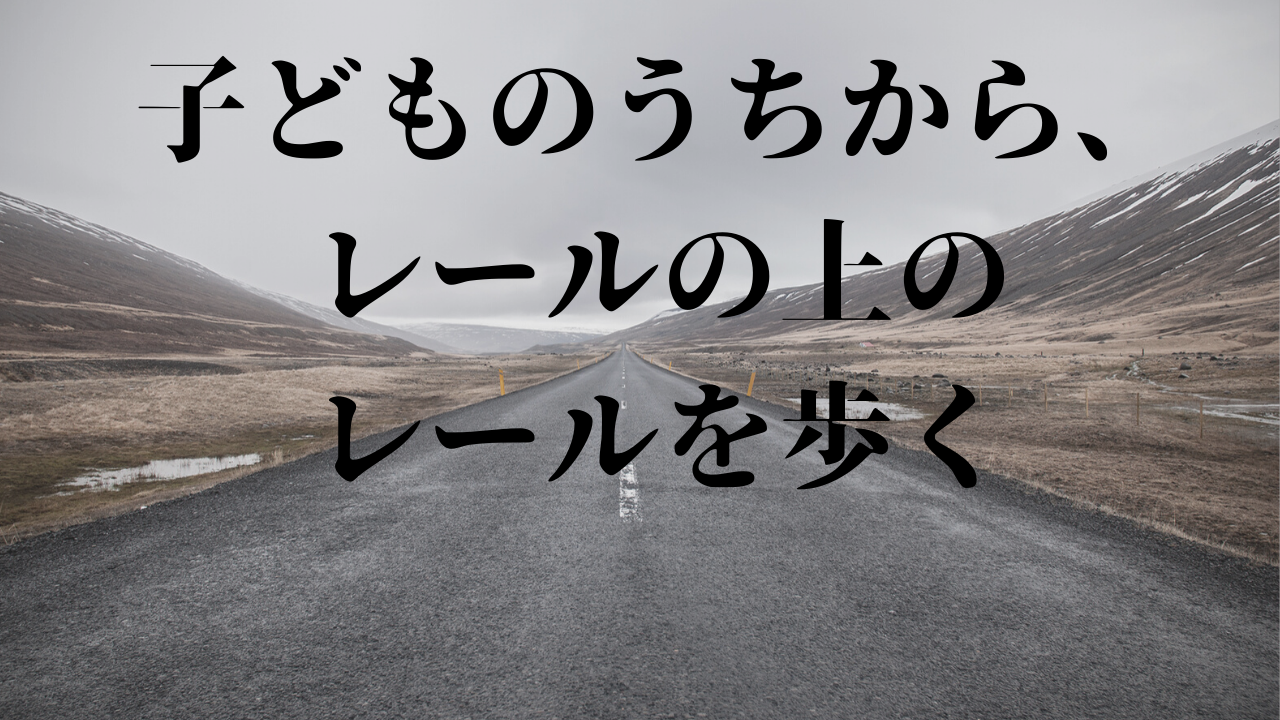「障がい」とはなにか 第5回
「障がい」とはなにか 第5回
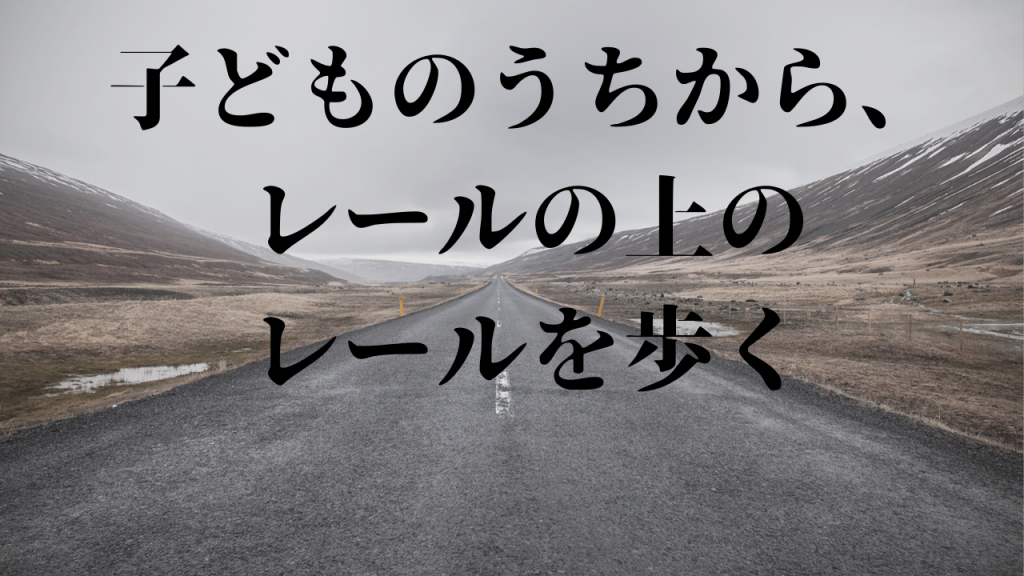
「私は、いつのまにか、レールの上の人生を歩いている気がする」と思ったことのある人は少なくないだろう。私の場合、正直、子どもの頃は今の私の姿を少しも想像できなかった。「親が死んだあとは、施設で一生、生活するのだろう」― 小学6年生で中学校の進路を決める時に、すでに将来が見えていた。
母親は、私の通学と学校でのトイレ介助に付き添いながら家事をこなしていた。父も兄も巻き添えになり大変だったと思う。障がいのある本人は、家族がもし亡くなっても、たとえ誰かが同情しようと、自分の障がいと一生向き合っていかなければならない。障がいがなくても、子どもは子どもなりに将来のことを考えているのと同じように、障がいがあっても(たとえ言葉に出さなくても)現実的なことを考えている。
小学生時代は、普通小学校に通い、母親がいつも車いすを押して送り迎えをしてくれた。母親は、授業中は待機し、トイレに行く時に介助をしてくれたり、教室移動の時は私を抱えて階段を上がり下がりしてくれた。
当時は、介助が必要な障がい者ほど普通小学校に通えるのがまれであった。その状況下でも、私の選んだ道を尊重してくれたのは、両親だ。就学前の教育相談では「○○養護学校に通いなさい」と言われたが、母親が「近くの学校に通いたい?」と私に聞き、私が「うん」と言ったばかりに、直談判で校長先生にかけあってくれた。最初に相談した学校では、「うちは前例がないから」と遠まわしに断られたが、母親は負けじと次の学校へ。その時に、ようやく「母親が付き添う」ことを条件に承諾を得た。
「母親にこれ以上苦労させられない、親から離れて養護学校に行こう」―12歳の私は、細かいことは言わずに「養護学校に行く」と告げた。学校の帰宅途中、私の車いすを押している母親に背中ごしに話をした。本当ならば友達とワイワイ帰る時間が、母親とふたりっきりの現実的な話をした時間だった。それ以来、中学校、高校と6年間は養護学校にかよい、学校に併設されている病院や寄宿舎で生活することになった。生活のすべての介助を先生方がやってくれるため、親に安心してもらえそうだという思いだけで選んだ。
もし、みなさんが「日本には、見えない人生のレールのようなものがある」と感じたことがある場合は、「障がい者」になると、そのレールの上のレールに乗っていると言ってもいい。私は、世の中に、みなさんが窮屈に感じるレールがあるから、レールがさらに乗っているのだと思っている。
時が少し経った20代後半の頃、福祉関係の支援者に講演をしたあとに「どうしてそこまでして一人暮らしをしたいと思ったのですか?」と質問されたことがある。「そこまでして」と言われて、少しイラだった。
確かに、子どもの時に「一生、施設生活だ」と信じ込んでいたら、そこから出て行く人に対して、どうしてそこまでして苦労する道に進みたいのだ?と思っていたかもしれない。
「障がい者」なのにそこまでして苦労したいのか?と思うこと自体に、社会の雰囲気の怖さを感じてしまう。エレベーターや平らなフロア、必要な介助を受けられる体制や仕組み、お互いに声をかけやすい文化があれば、それで随分と生きやすくなるのである。
私は、弱みや失敗の責任を個人に押し付けるのをよしとする風潮があるから、「障がい」を個人が背負うものだと勘違いしている人が多いと思っている。子どものうちから、人生を悟らせるようでは、この世の中終わりである。
もし、もっといろいろなアイディアを出すことで、いろいろな可能性が広がることを、身をもって実感できる人が増えていったら、世界はどうなっていくだろうか。レールの上のレールを歩かなくてもいい時代が来ることを信じるほかない。(つづく)