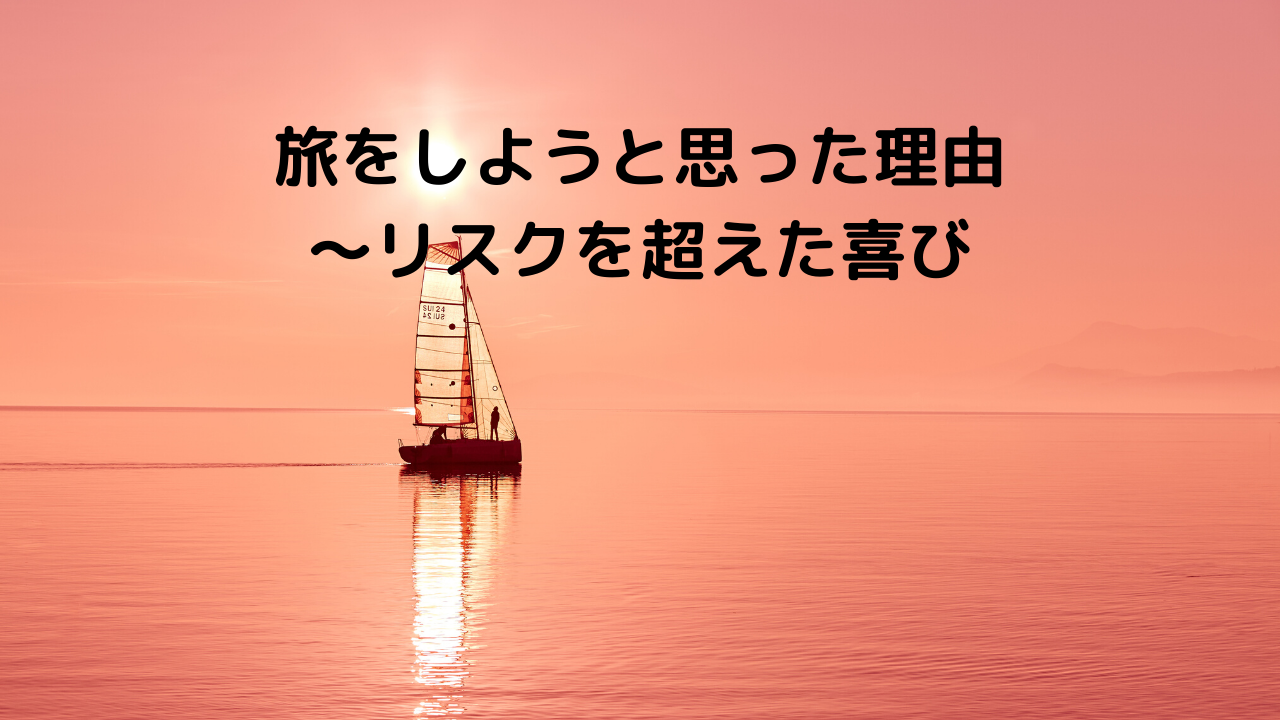目次/Contents
リスクの先に、新しい道をつくる
なぜそこまでしてリスクが高いことをするのか、見ず知らずの人に介助をしてもらうのか?と疑問に思う人もいるかもしれない。Michikoが社会に出れば出るほど、そのように思われることが多く、いつも何かをするたびに葛藤をして選択をしなければならなかった。でも、選んだ道には、どこにも得られない喜びが必ずあることを、大人になった今ようやく知るようになった。
小学校に入る前の頃、最初に記述したように、母親の付き添いを条件に普通小学校へ入学することができた。教室移動で階段を上らなくてはいけない時は、男性の担任の先生が抱っこをし移動をするし、車いすで移動する時は友達に押してもらっていた。もし、リスクだけを恐れていては、抱っこをする先生の体力が負担であるとか、生徒が車いすを押して誰かにケガをさせてしまったらどうするのかとか、心配事は尽きない。
実際に、ハプニングもあった。友達とハンカチ落としをしている時に、円になって座っているみんなの後ろを、友達が車いすを押しながら猛スピードで走ったら、遠心力で車いすが傾いて投げ出されたのだ。自分で体のバランスが取れないMichikoは、頭を床にぶつけてものすごい衝撃が走ったのを覚えている!!痛かった~。でも、風を切ってひやひやしながら走る快感の方が、捨てようとしても捨てられない素晴らしい思い出なのだ。
6年間通っているうちに、学校が広いトイレを作るようになり車いすでも入れるようになったり、グラウンドに行くまでの急な坂道がなだらかなスロープになったり、車いすごと階段を上がる昇降機がついたりした。Michikoが卒業した後も、車いすの子が入学していて、作られたものが活用されている。
入学前の就学相談では、相談員に養護学校しかないようなことを言われていたが、その助言を振り切って母親が自分で動き出すことになった。同じ小学校に先輩として通っていた車いすの女の子を知っていたからこそ、動くきっかけにはなり、ちょうど理解のある校長先生が赴任したことが重なって、入学することができた。車いすの女の子の情報がなければ相談員の助言が正しいと思ってしまうところだった、ふー、あぶない。Michikoが入学して6年間きちんと通えたことにより、車いすの子がいつ来ても大丈夫な環境が作られていったと思う。きっと、また色々改良されてきているんだろうな。
孤独でしかない〜介助中心の生活で、友人と過ごす時間を犠牲に
今度は、Michikoが母親の血筋を引き、大学へ入学して新しい道を切り開くことになる。中学生からカウンセラーになりたいという夢があったため、推薦で大学入試を受けることを決めた。
中学生から高校生まで決められた日課の中で職員に介助されながら生活していたため、社会に出ることは確かに怖かった。高校生であっても、地下鉄やJRに一人で乗ることが怖かったし、カラオケやファーストフード店、ゲームセンターなどへ遊びに行く経験もほとんどしていなかった。
大学に通い始めた当時は、ずっと母親にトイレ介助や、車いすを押す外出介助をしてもらっていたが、母親に頼っていては倒れてしまうし、自分の世界を切り開いていくことができないだろう。そう思ったMichikoは、学生ボランティアを募り、通学とトイレの介助を周りの学生にお願いすることにした。大学の先生の協力を得て、授業で募集の声掛けの時間をいただいた。
ところが、募集をする前に友人に相談をしたとき、「なんで危険なことをするのか、お金があるならヘルパーを頼んだらいいんじゃない?」と言われてしまった。現在は、福祉の公的な制度でホームヘルパーの介助を少ない金額の負担で受けることができる。大学の近くで一人暮らしを始めた時に、ヘルパーさんに来てもらいながら生活をし始めた。日常の外出もヘルパーさんを利用することができる。ところが、通学や通勤、大学や職場での介助は、すべて自己負担でしかヘルパーさんを利用することができない。時給1,000円~2,000円が普通だが、とってもじゃないけれど、毎日はかなりの負担であった。
確かに、入学してから2年程度はヘルパー派遣事業所が安価なサービスやボランティアで引き受けてくれていて、それに頼ってきた期間が長かった。でも、ずっと一日中いてもらったら多額になったり、ボランティアで長い時間いてもらうのは申し訳なかったりしていため、講義の後など時間を決めてきてもらっていた。トイレをしたくなくても決められた時間にしなくてはならない、講義の後に友人と話しながら次の教室に行くこともできず、ヘルパーさんのところへ急いで行かなければならない。行きも帰りも車を頼んで通学をしていたため、友人とたわいもない話をする余裕が全くなかった状態だった。
ふと我に返ったとき、お金を払うことで来てくれるヘルパーさんしか、私の介助の方法を知らないことに気が付き、言いようのない孤独感を持った。ヘルパーさんがいない時に、体調が悪くなったり、お腹が痛くなったりしたらどうしよう。さらに、身近にいる友人は介助のことを全く知らないどころか、時間が決められたヘルパーさんに合わせるために、友人と離れる時間がどんどん増えていった。
自然現象のトイレをすることに、お金をいくらかけるとか、どの時間にするとか考えることが苦しくなってくる。さらには、この人にしか頼めない、友人に頼んだら迷惑なんじゃないか…そんなことを考えて孤独感が増してくる。そこに、友人から「ヘルパーを頼めばいい」なんて言われショックだった。(誤解を受けないでほしいのは、友人も遊びに行った時はトイレも手伝ってくれた優しい人だ。Michikoも誤解をされるような言動をしたため、友人は反対をしたのだろう。)
「声をかけてみないと、賛成の人も出てこないよ」
ショックを受けた頃、ちょうど大学の先生の協力でボランティア募集を始めようとした時だったが、「みんなにとって迷惑なのではないか、募集をかけることをやめたい」と先生に涙を流しながら、打ち明けた。
先生は冷静にうなずいて話を聞いた後、このようにMichikoに告げたのである。「そりゃあ、中には反対する人もいるかもしれない。でも、声をかけてみないとわからないよね。反対する人もいれば、やりたいと力を貸してくれる人もいる。ここでやめてもいいの?」
その先生の言葉がなければ、介助者なしでタイとイタリアに行くMichikoは、いない。その後、勇気を振り絞って、講義で募集の呼びかけを行ったり、先生が声をかけてくれた5,6名の学生を集めて「私は、トイレ介助が必要なんです」ということを丁寧に説明した。通学時に車いすを押す介助も募集をし、そこでは男性も含めて呼び込むことにした。
この大学ではもともと、聴覚障害がある学生や筆記が難しい学生へのノートテイク(先生の話を文字に起こす、黒板の内容をノートに移す)のボランティアが盛んだったが、車いすを利用する学生への通学介助やトイレ介助はされていなかった。
前例がないなら、前例を今からつくる
また、ここでも前例がないところに道をつくっていく。結局2年間でトイレ介助のボランティアが10名弱、通学介助が20名程度集まった。一人ひとりができる範囲で無理なくボランティアをしてもらえるように、希望を聞いて毎週・毎月シフトを組みながら、大学生活を送った。
大変であったが、色々な人に頼める体制ができたことで、急きょ困ったときにも助けてもらえる環境ができた。また、通学ではお互いに何気ない話をしながら、車いすを押してもらい、普通の大学生の日常を送ることができたと初めて心から思った。Michikoが卒業した後、ノートテイクを行っていたボランティア団体も「介助部」という部門を作り、通学介助を組織的に行っている。
さらには、大学側は何かあった場合でも責任は取れないので、全面的に支援はできないと言われていたが、個人的な行動で行うことを暗黙の了解として見守ってくれていた。それがわかったのは、卒業式の学長の挨拶で「優秀な学生」を紹介した時だった。何人かのエピソードが紹介された後、ボランティアの力を借りながら学生生活を果たした、Michikoのエピソードが紹介された。その時はなんか聞いたことがあるなと耳を傾けていると、次第に自分のことだとわかり、胸がじわじわと熱くなり涙が溢あふれそうになった。
リスクが高いと、やっぱりリスクがある
初めての試みだったため、大学の先生も内心は不安な気持ちもあったと話していた。トイレ介助で体を持ち上げた時にケガをしたらどうするのか、通学介助で事故に遭ったら大変だ、学生が急にキャンセルして来なくなったらどうしようか…心配は正直に言って尽きない。
実際に、トイレ介助では床に落ちそうになったこともあるし、学生が予定の時間に来ないこともあった。逆に、私も忘れてしまって待ち合わせの時間に遅れることもあった。そのことで、関係がぎくしゃくすることもあった。雪道で車いすを押してもらった時は、車いすが雪に埋まり動けないこともあった。冬の通学では2名体制で行っていたが、汗を垂らすほど辛い思いをさせたこともあるだろう。
Michikoが色々なことに挑戦しようとするほど、リスクが高くなる。さらに一人でできるわけではないので、そのリスクは周りにも分けることになる。そこをどうやって折り合いをつけていくか、それはやはり、洋服店のショートカットの店員さんにトイレ介助をお願いした時のように、お互いの対話が必要になってくると思っている。
安全に行うための方法や危険になった場合の対処方法は事前に話し合い、お互いに予定が急に変更になった場合の連絡方法を決めておく。介助で体を少しでも痛めることがあれば、遠慮せず報告してもらうように頼む。そういったことが当時どこまでできていたのかわからない。どうしてもボランティアが遠慮してしまう時もある。確かに100%安全なんてありえないけれど、リスクを少しでも避ける方法を考えてきた。
障害があろうがなかろうが、外に出るだけで事故に遭う確率が高くなると考えると、みんな外に出なきゃいい。でも、学校や職場に行かなければならないし、遊びにだって行きたい。旅行もしたいし、スポーツもしたい。そして、Michikoも同じ。
ただ、障害があることによって、リスクが高いように見えたり、責任はだれが取るのか?と周りだけが考えたりしてしまう。確かに人よりもできないことが多いかもしれない。
しかし、障害があると、危険を予測して行動する力があるとも言える。
そうして、Michikoは、たくさん外に出て行ったことによって、ヘルパーやボランティアとの関わり方を学んだり、海外旅行の行き方を知ったり、チェアスキーで横に倒れた時の受け身の取り方を覚えたりと、リスクとの関わり方を身に付けていった。
追記
この記事は、2012年11月2日から12泊13日でタイとイタリアへ旅をした時のノンフィクションの物語です。以前に本を出す予定で書き溜めていたものですが、色々とあって出版には至っていませんでした。
それを知った友人が「それはもったいない」と言い続けてくださり、最近ようやくこちらに載せようと思い始めました。
連載ものになっていますので、ぜひゆっくりと読み進めてみてください。
今では、新型コロナウィルスの影響で、タイやイタリアに住んでいる友人や出会った人々が元気に過ごしていらっしゃるか、心配しています。
友人に気づいてもらえたら嬉しいなという思いで、連載で載せることにしました。
どうかお元気でいらっしゃることを願って。