私は、週の真ん中あたりに、ことば遊びをする気分になるようだ。今日は、「障害受容(しょうがい・じゅよう)」についてを考えてみる。(ちなみに、過去にそれについて書いた記事はこちら→「障害を受容する」はカメが歩いているのを観察するようなもの、理学療法学科の学生さんへ~知識では終わらない大切なこと)
パッと見て、四字熟語みたい(笑)説得力がありそうなイメージがついてくる。前にも、同じテーマで書いたが、不思議と年齢を重ねるにつれて、考え方も変わってくる感覚がある。
受容は「受け入れること」という意味でokだとすると、何を受け入れるのだろうか?医療や福祉関係の教科書では、自身の体や心の障害を受け入れるという意味で書いてあることが多い。それには何段階かあって…ということを習ったが、もう忘れた。
本人が幸せになっていく意味で変わっていくのはイイね!と思うだけで、それ以上は他人が評価するものではないと思う。「あの人は、障害受容していない」「あの人は障害を受け入れて、輝いて見える」「あの人は、障害受容のレベルでいうとこの段階だ」と考えるのは、ほとんど専門家と言われる支援者である。私も言われたら、腹が立ってしまう。私の家族や大切な人にも言ってくる人がもしいたら、げんこつをしたい。
そもそも、自分のことを受け入れるということ自体、一人でできることでもないし、環境が自分に合っていれば、そんなことも考えずに生活できるのではないかと思う。まず、私は自分に対しても、他人に対しても、「障害受容しているか。していないか。」という考えを持っていない。障害のある人には言われたことはないし、日常の会話でも使ったことはないが、支援者には言われたことがある。と考えると、やっぱり日常生活には必要のないことばなのかもしれない。
外に目を向けてみると、車いすでは上がれない段差や階段、狭いトイレ、健康な人しか働けない職場環境など、「環境にある『障害』」はまだまだある。それらを受容している人が多いから、変わっていくスピードがかなりゆっくりだなと思う。この場合の障害の受容はしない方が、もっと広く、大きくイイことがありそうだ。
これからは、障害は受容しないほうがいい、障害を受容しない人が集まったら、百人力である。
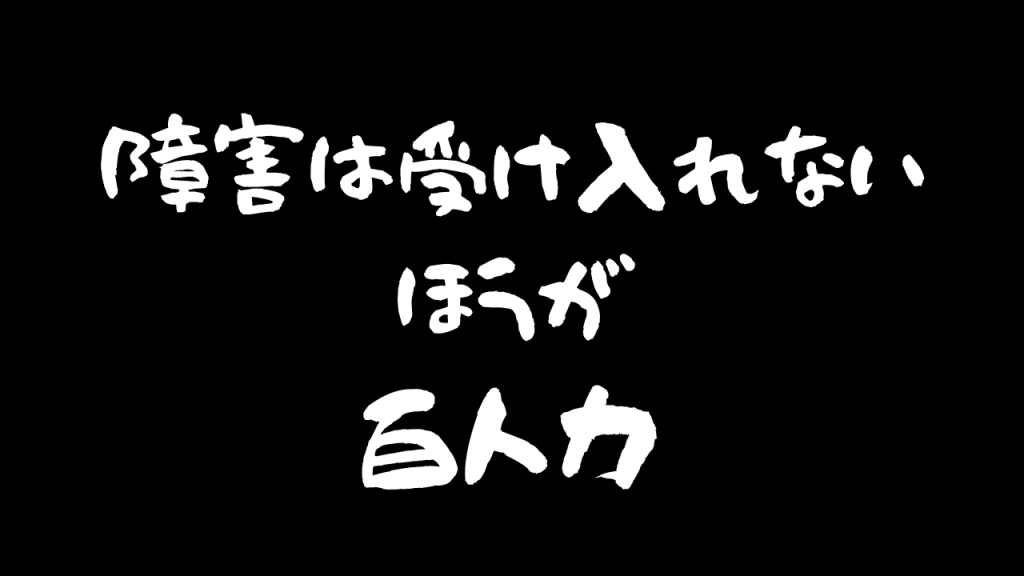

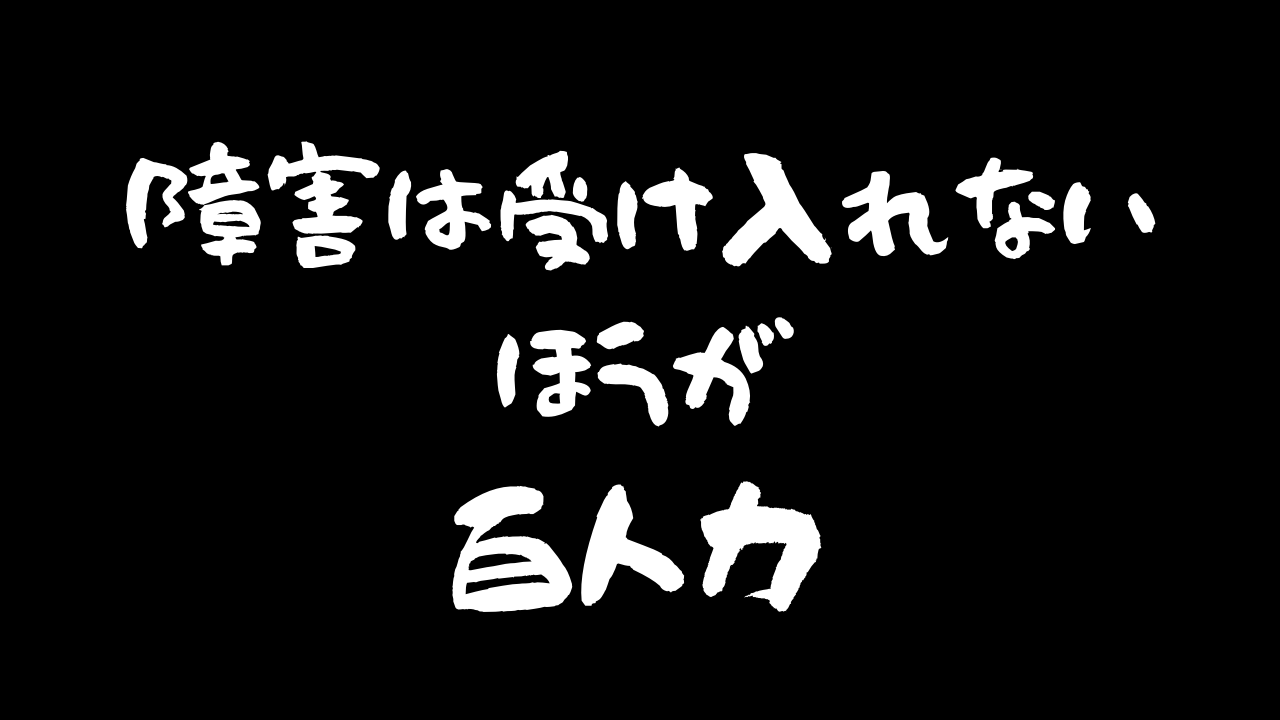















登り口さん、こんにちは。
いつもあらゆる視点から、福祉や障がいにまつわる
記事を投稿していただき、有難うございます。
さまざまな経験を辿ってきた、登り口さんの障がいに対する考え方に触れるたびに、自分の思考も柔軟になるような気がします。
「障害は『環境』にある」、「環境による『障害』を受け入れない」。
このような想いを支援者側に伝える勇気も必要で、伝え方や支援者によって、どれだけ受け入れてもらえるかも、きっと変わってくるのだと思いました。
また、登り口さんの文章力や表現力には関心することが多々あります。
わたしは、周囲の気持ちや考えを察して受け止めつつ、自分の気持ちを適切に伝えることが苦手なので、自分の気持ちを書き出して、整理をしていきたいと思いました。
長文になってしまいましたが、最後まで読んでいただき感謝です。
静岡県在住
脊髄損傷 車椅子ユーザー
ノゾミ
のんさん、こんにちは。コメントの公開が遅くなって申し訳ありません。
なかなか人に伝えることって難しいですよね。
自分の頭の中にある考えを文字にしたり、言葉にして話したりしようとしても
全てを伝えられないので、いつももどかしい思いでいます。
私は、自分に気力がある時は、スマホなど、自分がやりやすい方法で思いを書き出すことをしています。
気力がない時は、無理せずに、できるときにやっています。
書くことは、いつでも修正できるのでいいのですが、
話すことは、その場で発した言葉で勝負することになるので難しいです。
いつも迷いながらのブログですが、
そのような感想をいただいて本当に嬉しいです。
※コメントの最後に、お名前や在住場所を記載していただいていましたが、
公になってしまうため、こちらでカットさせていただきました。