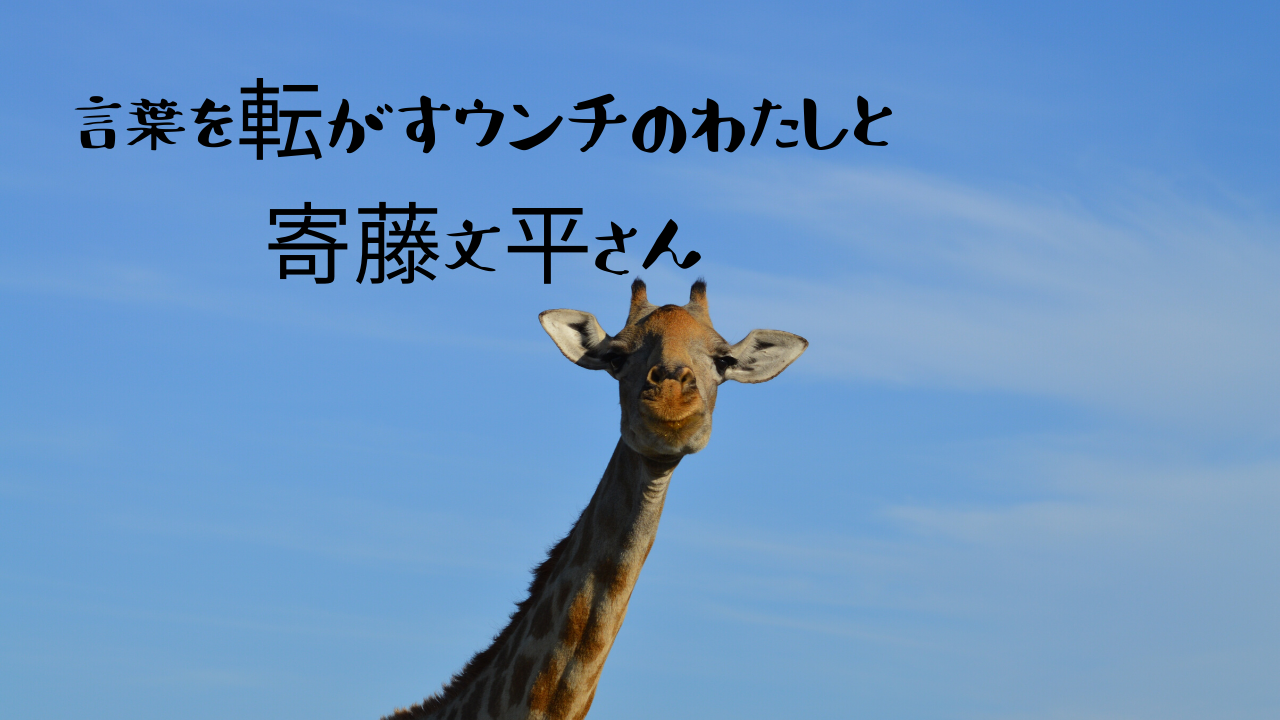再び、本の出版ができないかと思い始めている。一方で、本の出版が目的ではない気もしていて、わたしの心に何が泳いでいるのかを探って見たほうがいいなと思った。
いつのことだったか忘れてしまったが、何年も前に、自分の本を出そうとある編集者さんとやりとりをさせていただいた。そのときは2013年くらいのイタリア旅行を交えて、自分の半生を書いた。12万字くらいは書いただろうか。しかし、あっさり本の出版をあきらめてしまった。自分の文章が気に入らなかったし、本をつくる過程がまったく楽しくなかったからだった。
当時は、わたしにとって書くこと自体がすごく苦しかった。書きたい気持ちはあったが、どのように書いていいのかわからないまま、絞り出していったという感じだ。今は、気力がないときはうまくアイディアが浮かんでこないが、そのほかは、日常からアイディアの断片(ピース)みたいなものが、いたるところに動き回っている。取ろうとしても、それを膨らまそうとしても、追いつけない感覚だ。
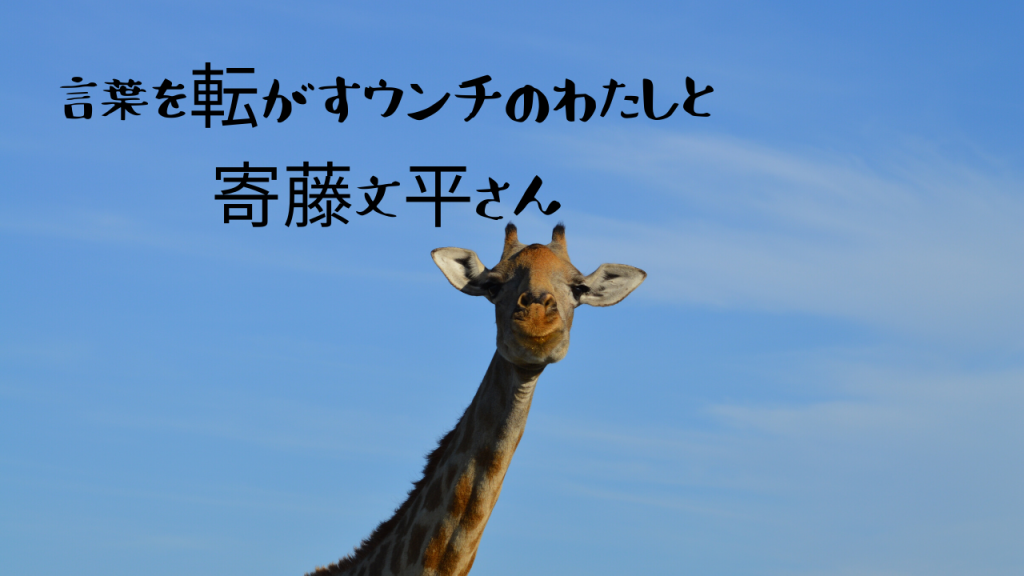
「ウンココロ」を描いた寄藤文平さんは、長年、さまざまな本のデザインを担当した中で、「自分にとってデザインとは何か」ではなく、「デザインにとって自分とは何か」を考えるようになったという。(著書「デザインの仕事」より)
アウトプット(発信)についても興味深い言葉があった。相手を説得・納得させるプレゼンのうまい人のように「人に勝つためのアウトプット」ではなく、「自分にとって本当のこと」を表現できているか?ということが重要なのではないかと。
例えば、わたしのブログ活動で例えるならば、寄藤文平さんの言葉をすぐに消化できないでいる、その動きそのものも「文章表現の中のわたし」ということである。
わたしは、いろいろなYoutubeを見て、弁がたつ方が視聴者数が多いので、そういう風にならないといけないのかなと思っていた。見ている側にとっては、確かにわかりやすく、中毒のように見てしまうのだが、一方のわたしは、「わたしがやるのはこういうことではない」と考えていた。
寄藤文平さんの本を読んで、わたしの中のことが少し見えてきた。さまざまな変化の中で「これはどういうことかな、わたしはどうしたらいいかな、相手にとって何が必要かな」と考える途中を表現することで、いろいろな人の役に立つことがあるかもしれないと思っていたことに気がつく。
少し話がそれるかもしれないが、わたしは、言葉の使い方や表現の仕方にかなりの関心があるようだ。これは、あえて「ひらがな」にしたほうがいいとか、「漢字」にしたほうがいいとか。「私」を「わたし」、「色々」を「いろいろ」などと、「言葉の転がし方」がブログの中の記事によっても違っている。本なら統一しないといけないが、ブログだと好きなように表現できるから、自分に合っているのかもしれない。
寄藤文平さん自身も「売れる表現」「本に合った表現」とのせめぎ合いの中で、著者や編集者とともにバランスをとっていく作業に、自分は何者であるべきかを日々考えてきたように、わたしは感じた。
ということは、わたし自身もこのブログを通して、わたしの出現のあり方を模索しているのかもしれない。うにゅっとウンチのように出てくるか、パンっと弾けるように飛んでいくか、出てきてもいいですか?とモグラのように頭を出して確認をしてから出てくるか、アリのように何かを運びながら足早に目的地へ行くか…想像すると無限に出てきそう。
わたしは、最初の「ウンチ」が一番好きである。前世は、「言葉を転がすウンチ」だったかもしれない。そんなわたしから出てくる表現を最大限楽しめることを考えよう。それが本なのかどうかは、まだ検討しよう。