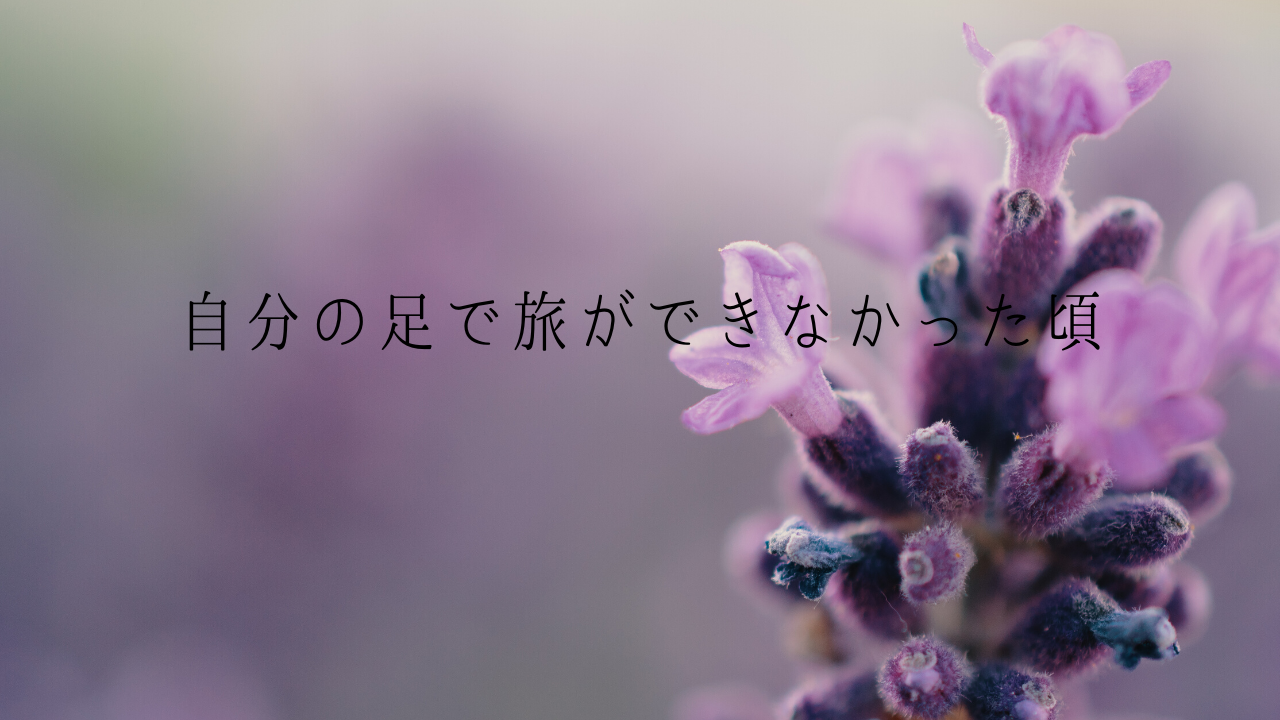目次/Contents
Michiko、電動車いすと出会う
Michikoが電動車いすを手に入れたのは、もうすぐ中学生になる小学6年生のとき。毎月リハビリで通っていた病院で、体の寸法をはかり、初めて電動車いすを作ってもらった。
できたばかりの新品の電動車いすに乗った時の感動は、今でも忘れられない。ジョイスティックという棒状のコントローラーを360度動かし、自由自在に動くことができる。話をしている人の方を振り向いてみたり、きれいな音楽が流れていることに気づいてそっちを見たり、でかい虫が襲いかかってきたら車いすと「一緒に」猛スピードで逃げてみたり、動きたいその時!!に動くことができるのは大きな感動である。
それまでは、手動で動かす車いすで、いつも親や友達に押してもらっていた。なぜなら、「体幹機能障害」という名の腹筋でバランスが取れない特徴があるため、肩や脇を締めてバランスをとっていて、腕を横に伸ばすことが難しかったからである。きっと10分くらいかけて1m進むくらいである。
「鉛の足」でレールの引かれた人生を歩く
他人に車いすを押してもらうことは、レールの引かれた人生を歩むことと同じである。
普通小学校に通っていた頃は、ずっと自分の手で動かす手動の車いすだった。次の教室へ移動する時には、母親に押してもらうが、真っ直ぐ目的地の教室に行くことになる。違うクラスの友達のところに行って、「やっほー」と声をかけることができないし、机に入ってしまうと、向こうの席で楽しそうにしている友達のところに飛び込むこともできない。「私もそっちに行きたい!」「みんなこっちに来て!」なんて、声すら出ないほど、人見知りが強かった。
小学1年生の頃、休み時間になるたびに、周りの同級生が車いすをめずらしそうに見てやってきていた。特に小柄で、普段からちょこまか動いて遊んでいる男の子が「押してみたい」と言って、Michikoちゃんが「いいよ」と言わないまま、勝手にグルグルと廊下や広場を駆け巡って走っていた。もちろん、Michikoちゃんは乗ったままで、後ろからやみくもに押されているので、目が回って仕方がなかった。
ショッピングに出かけたときには、買おうと思っていたもののところには行けても、その途中で偶然見つけたものに気持ちが惹かれたときには、通り過ぎてしまったりと、気持ちと行動が一緒にならないイライラ感がある。目的の場所にはたどり着けても、寄り道がしづらいのが悲しいところである。(人生は、寄り道があるからこそ楽しいのにね~。)
学校の帰り道だって、休日に友達と遊ぶときだって、家にいるときだって、車いすはMichikoにとっては「鉛の足」のようだった。その気持ちを伝えればいいと思うかもしれないが、そうもいかない事情がある。「押してくれているのに申し訳ない」という気持ちがあった。
Michikoは、「動きたいのに動けない」「自分で何もできず他人に迷惑をかけてばかり」という気持ちでいっぱいになり、その状態に耐えられなくなった。学校の帰り道で母親に「中学は養護学校に行く」と伝えるのであった。特に行きたいわけではなかったが、養護学校に行って親から離れて暮らすことで親も楽になるだろうと思った。それは親思いと呼べるほどきれいなものではない。大切な人が辛そうなところを見ると、自分が悪い存在かのように錯覚してしまい、恐怖だったのだと今では感じている。本当の気持ちを奥に入れてしまうMichikoちゃんが、急速に成長してしまった。
Michiko、「他人に合わせる術」をマスター
中学生からは、親と離れて養護学校に併設されている病院で「生活の訓練」を目的に生活することになった。病院は、体や知的に障害がある子どもが入院しており、手術を目的に住んでいる人や、生活の訓練のために住んでいる人がいた。
朝は、決まった時間に看護師さんが動き出し、一部屋ずつ回っていき介助が必要な人をベッドから車いすへ移動させることから始まる。40人の子どもに対し、朝は3人ほどの職員が見回るため、順番が回ってくるまで待たなくてはならない。逆に、最初の方で起こされることもあり、ゆっくり寝たくても寝られない状況にもなる。起きてから朝食の時間まで30分程度しかない。着替えたり、洗面をしたりすれば、すぐに時間が来てしまう。学校から帰ってきた後にすぐに入浴である。夕食時間が5時くらいだった気がする。夏なんて明るい時間から夕食を食べていた記憶がある。そのあとは学習時間で勉強をしていた。1時間勉強してから、やっと自由時間。テレビは1台のみ。当然、多くの人が見たいチャンネルを入れることになる。そして就寝は9時ころ。
職員の流れ作業の中で生活をしている気分になる。特に、嫌だったのが入浴。介助が必要な人は学校から早く帰ることが求められ、急いで脱衣室へと入っていく。入れば、先ずは脱衣室にいる職員が服を脱がせる。次に、浴室で洗う職員がMichikoを二人で抱えて蛇口の前で座らせる。洗い終わったら、浴槽へ抱えていき、手すりに体をつなげて固定される。脱衣室にいる職員の手が空いていると、雰囲気で上がってほしいことがわかる。床に敷いたタオルに寝かせられて着衣をする。他にも介助が必要な人が浴槽から上がってくると、二人で仲良く並んでいることがあった。着衣が終われば、頭を乾かしに行く。ドライヤーを持っている職員が待ち構えている…。ドライヤーをかけていると、たまに後ろで待っている人がいる。髪形など整えるほど時間はないため、乾いたらおしまいである。
入浴は週に2回程度であるが、その他の一日の介助も決まった時間の中で行われていた。この生活の中で、どんどん受け身になっていく自分がいた。そこでさらに追い討ちをかけることになったのは、看護師さんから「人に何かしてもらったときは、『ありがとうございます』といいなさい」と注意された言葉だった。複雑な思いを持っていても、言い訳はせず「はい」と返事するのが精一杯だった。他人を思いやり、「ありがとう」と言わなくてはならないことを心の中で誓った。
それでも、ありがとうなんて言えないほど嫌な時だってあった。それは、男性の看護師によるトイレや入浴介助であった。たとえ男性の職員であっても、陰部は拭くし、全身を洗ったりする。中学生なりに「これは嫌だ」と思い、女性の職員に訴えた。けれど、「看護師として仕事でやっているのだから問題ない」「わがままだよ」と言われてしまい、ショックを受けた。いや、ショックを受けたというより、「そんなもんなんだろう」と自分に言い聞かせたと表現した方が良い。
高校は別の養護学校に通い、引き続き親から離れて寄宿舎生活をすることになる。周りの大人の職員に毎日介助してもらう生活は、中学生の病院生活と雰囲気は変わらない。ただ、高校の寮だけあって、就寝時間も遅いし、異性介助は全くない。しかし、「学校から早く帰ってきて、入浴を早く済ませてほしい」という空気は同じくあった。入浴が週2回だけなのは、高校生で成長期にいる中で地獄だった。髪の毛がどうしても脂っこくなったり、体も臭いがする気がしてイライラしてしまう。洗面所で髪だけも洗いたいと思い、手が空いている職員を探して頼むのが「毎日必死だった」のを今でも覚えている。
朝の朝食前に飲もうとして、職員に野菜ジュースを冷蔵庫から出してもらったら、別の職員に怒られてしまった。「時間に余裕がなく、職員の手が足りないし、ひとりにかまってられない」という理由で却下されてしまったが、朝食後から登校まで30分しかないため「お便をゆっくり出す時間がない」のもわかってほしかった。そのようなことを聞いてくれる職員はいないことがわかり「言っても無駄」であきらめた。
13歳には、自分の思いよりも周りの大人の顔色を見ながら「言うことを聞く」という「他人に合わせる術」をマスターしてしまった。電動車いすを初めて手に入れて、目をキラキラさせるほど喜んだ記憶も、遠い昔になってしまう!
でも、車いすとの出会いが、中学・高校生活、大学生活へと生活の幅を広げたことは、まちがいなかった。そのことを、中学生のMichikoには、まったく想像がついていなかった。
電動車いす1号とバングラデシュへ~そして1台だけで世界へ
初めて買った電動車いすをでんくる1号と名付けよう。でんくる1号は、12歳から25歳くらいまで一緒にいた。といっても、1号ちゃんは坂を上がろうとすると前輪が浮いて後ろに倒れやすく、腹筋が働かないMichikoは、後ろにそのままひっくり返り、頭を強打する事件が発生。高校生からは他のタイプに変え、1号ちゃんは部屋の隅にねむってしまうことになった。
24歳の冬、1号ちゃんの出番が思わぬところに来た。まさかの海外進出、バングラデシュの旅へ。しかも、初めての海外である!
NPO法人「飛んでけ!車いす」の会(日本で使われなくなった車いすを、主に発展途上国に送っている国際協力事業の団体。)のボランティアメンバーと一緒に、年1回のスタディツアーでバングラデシュに一緒に行くことになったのだ。(私も会のボランティアに関わっているメンバーである。)
当時、高校の寄宿舎生活から出て大学も卒業し、社会人になった頃で、色々活動の場を広げていた。「飛んでけ!車いす」の会と出会ったのは、そこで車いすの整備のボランティアをしていたKojimaさんというおじさんが、「スキー、やろうよ。チェアスキーがあるから一緒にできるんやで」とナンパしてきたところから始まった(笑)その男性は、私が2回目に入学した大学で出会った方だった。私は、自分で体のバランスが取れないし、ブレーキをかけるストックも持てないからできないと思っていた。けれど、後ろで一緒に操縦する人と息を合わせて滑ると、気持ちよく雪の上を滑ることができた。しかも、公園の雪山ではなく、スキー場で。「できないのではなく、方法を知らないだけだよ。」と教えてくれた。
そこからその男性を通じて、団体に関わるようになり、その中心的なメンバーのかずちゃんと遊ぶようになった。ある日の帰り道で「一緒にバングラデシュに行かない?」と誘ってくれた。「今度食事でも行かない?」という誘いと同じくらい、あまりにも自然すぎてびっくりしたのを覚えている。
今までは、「自分は障害者だ」と思っていた。幼い頃から「自分の体は治療の対象」だと思っていたし、小学生からは「自分は何もできなくて、他人に迷惑をかけている」と思っていたし、病院や寄宿舎でも「お世話されている人」であった。私は、そのような社会しか知らなかったのである。
でも、「自分は人であり、女性であり、ただ歩く手段が車いすなだけ」なんだって思うようになっていった。医療や福祉の世界から外に出てみると、ナンパおじさんやかずちゃんのような人がたくさんいることに気が付く。読者の方には、「私は障害者と話したことないし、わからないよ。ましてや友達なんていないよ」という人が多いかもしれない。たしかに、私が出会った人の中でも、そのような人たちが多かったし、私自身が高校を卒業した後、収容所から出所したかのように、周りの目線が怖かった。
実際にわかったことは、「障害者と関わったことがない、知らない」というところから出発した方が、関係を作ると「新鮮で驚きの体験をした」と思ってくれる方が多い。
たとえば、バングラデシュに行く前のことである。実際に自宅の普通のお風呂場を使い、大学生にお風呂介助を実際にやってもらったり、雪道の中で車いすでの外出を手伝ってもらうことを行い、1週間以上の旅に備えた。
旅行中は7,8人の女性の学生が交代で手伝ってくれた。その学生は、福祉とは違う専門の勉強をしていて、介助をしたことがない。旅行中は、慣れない環境の中で疲れがたまってくる上に、体を抱えることもあったため、大変だったと思うが、そんな顔は一つも見せず返って楽しみながら介助をしてくれたことが一番うれしかった。その後も、ずっと関わりがあり「貴重な経験だった」と言ってくれた。これが一つのきっかけでホームヘルパーの資格を取った学生もいたほどだった。
この大きな旅を一緒にしたのが、でんくる第1号。1号を選んだ理由は、もうかなり古いし今は使っていないので、旅先で壊れても安心であるということ!ごめんなさい!!(笑)
でも、その選択は間違っていなかったと思うほど、バングラデシュはすごかった!!!バングラデシュに着いたときに、自分の車いすは荷物として出てくるため、その前に航空用の車いすに乗る。その車いすがなんと、タイヤがほとんどすり減り、部品の一部がなかった…。ワゴン車で移動するとき、車いすを積むときが荒かったし、中道を入ると車道の整備がされていなくガタガタ。それでも、でんくる1号はケガを一つもせずに日本に帰ることができた。良かった、良かった。
その後、1号のバッテリーが消耗して使えなくなり、本当にお役目がなくなってきた。そのときに思いついたのが、まぎれもなく「飛んでけ!車いす」の会に寄付し、どこかの国に届けてもらうことだった。どこに行っているのかわからないが、険しい旅を乗り越えてきたでんくるは、必ず誰かの役になっているだろうと、今も願っている。
今度は、「自分の足」で旅をする
2012年6月、バングラデシュから帰ってきて3年後、今度はある決心をする。介助者は連れて行かず、現地の人に助けを自分で求める「ひとり旅」をしようと考えた。ひとり旅を決めたのは、バングラデシュで後悔したことがあるから。それは「自分の足」で旅をしなかったことである。英語ができる学生に現地の人との通訳や、空港職員と車いすを荷物として預かるときのやり取りも任せ、何もかも助けてもらった。
この旅は、先述したように、介助者ではなく学生だけと旅をする大きな経験になり、本当に楽しかった。けれど、言葉ができるようになって、「自分の足」で旅をしていきたいという気持ちが強くなった。
一からやり直したかった
「他人の手を借りながら生きること」
もうひとつ、「他人の手を借りながら生きることを、最初からやり直したかった」のだ。
幼いころから介助をしてもらう生活をし、「他人の手を借りることは迷惑で、自分の気持ちは押し殺さなくてはならない」と思ってきた。もっとたくさんの人と出会うと、「他人の手を借りることで、周りに新しい影響を与えるし、新鮮な関係を結ぶことができる。そして、色々な可能性が広がる」ということを知った。むしろ、押し殺すのではなく、必要な手助けはどんどん発信することが大事だとわかった。
しかし、そこに再び、「できないことがあることは、無力だ」と落ち込む出来事が出てきた。
それは、ひとり旅を決心した2012年。就職活動を始めて3年が経とうとしていた頃だった。ハローワークに何度も通ったが、求人票には「車いす移動不可」「自力で通勤できる人」が条件として書かれ、トイレ介助が必要であると話がそこから進まなかった。最初は、自分ができることを全面的に履歴書に書き表していったことで、面接には進んだ。しかし、現実的な話になっていくほど、「外出の場合は車いすを押してもらうか、タクシーが必要」だとか、「トイレは必ず介助が必要」だとか言わなくてはならない。当然、10分程度の面接で、その解決策をあみ出せるわけでもなく、そこで話が終わって不採用となり、会社と話し合うことさえもできない。(私の自信がなかったせいかもしれない。)
どうしたら、通勤や介助を支援してまでも雇いたいと思ってもらえるか?専門的な知識があって、パソコンもものすごい速さで操作できて、社会性もどんな人よりも優れていて、仕事を人一倍効率よくできるパーフェクトな人間なら、良いのだろうか…本気でそんなことを考えたことがある。
再び、「自分が障害者である」ことを目の当たりにした。「歩く」「トイレに一人で移動し着脱する」「外で自分で車いすを操縦する」ことは、自分ではどうしようもできなかった。できないことは言わなくては生きていけない一方で、できないと言えば仕事をすることができない。本来ならば、通勤やトイレ介助を支援できるしくみがあれば、障害がない人とスタートラインは同じだっただろう。スタートラインに立つまでが大変であったため、働いている人が文句だけ言って努力しない姿を見ると、腹立つ思いでいっぱいだった。努力をするチャンスすら奪われていると心の底から思った。
「他人の手を借りながら生きる」ということはどういうふうに考えればいいのだろう。Michikoは、「助け合う」というきれいごとでは考えられなくなった。
人を助けることができないと卑屈になるMichiko、
社会は不公平だと恨むMichiko、
安易な気持ちでも、テキトーにアルバイトができてしまう若者をうらやましく思うMichiko。
ダークなMichikoちゃんができあがりそうだった。
Michikoは、その状態から抜け出し、もう一度やり直したかった。だからこそ、だれもMichikoのことを知らないところへ一人で行き、生きてみたかった。自分で頼まなければ、死んでしまうと言っても良いくらいのサバイバルな旅をすることを決めたのだ。
追記
この記事は、2012年11月2日から12泊13日でタイとイタリアへ旅をした時のノンフィクションの物語です。以前に本を出す予定で書き溜めていたものですが、色々とあって出版には至っていませんでした。
それを知った友人が「それはもったいない」と言い続けてくださり、最近ようやくこちらに載せようと思い始めました。
連載ものになっていますので、ぜひゆっくりと読み進めてみてください。
今では、新型コロナウィルスの影響で、タイやイタリアに住んでいる友人や出会った人々が元気に過ごしていらっしゃるか、心配しています。
友人に気づいてもらえたら嬉しいなという思いで、連載で載せることにしました。
どうかお元気でいらっしゃることを願って。