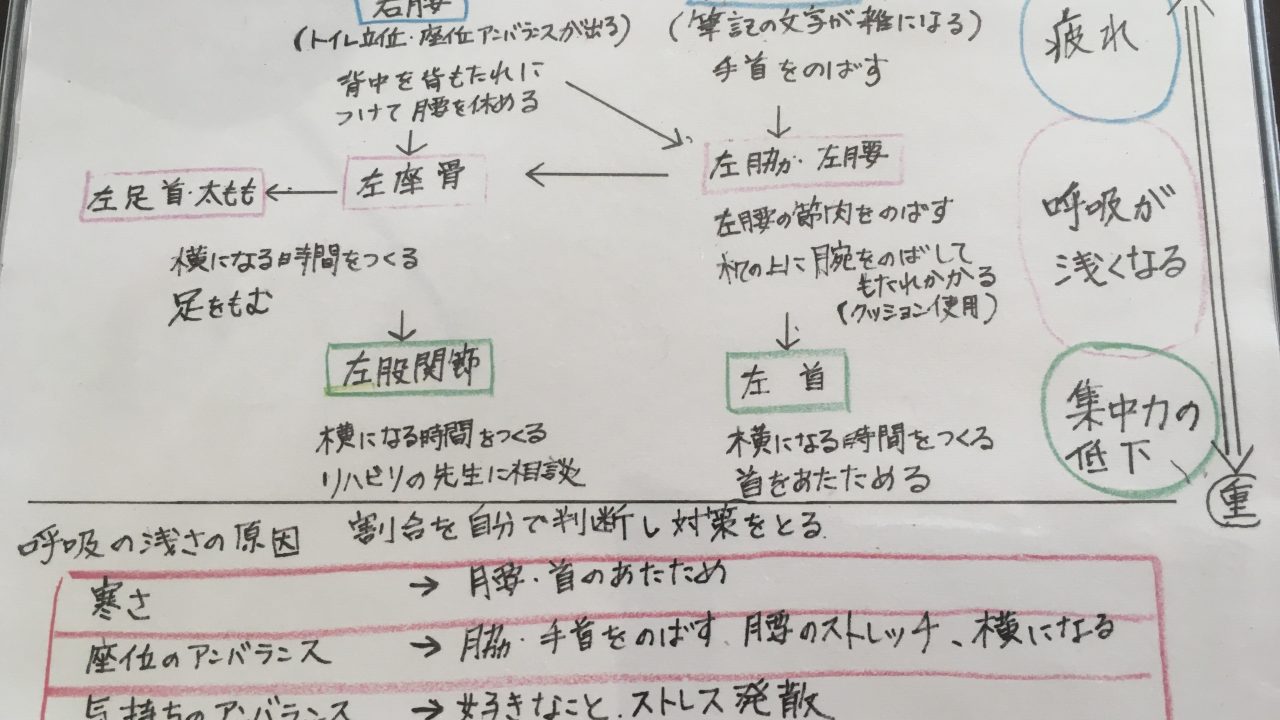疲れを放っておくと、いずれは体が痛くなり、精神的にも「もういやだな。」と参ってきてしまう。障害のある人や高齢の方は、毎日のように体の負担を感じている。案外、健康と言われている人々の方が、最後の最後まで頑張ることができてしまうために、気づいたときには、体も心もボロボロになっていくことが多いかもしれない。
私は、これまで、体の不調のサインを感じとる方法を考えてきた。今日は、自分で体調をコントロールする方法を考えてみたい。
「これやばい」と最終レベルの体調不良をイメージ
下の写真の図式は、私の体調の変化のパターンを矢印を使って流れを描いたもの。体調の変化があっても、どうしても働きたくて、いろいろ自分の体調の分析をしていた。

まず、下のリストについて、考えてみる。青字が私の場合。
青字の部分を、自分の状態に当てはめてみよう。
- 私は、最終的な体調の悪さは、「頭痛」だ。
- レベルは、「思わず口に出したくなるほど、痛く、我慢できない状態」
- その状態では、「寝込んでしまって、仕事も生活のことも何もできない」
- 本当は「回復も遅いし、辛いし、やりたいことができないので避けたい」
①最終的な体調の悪さは?
↓
②そのレベルは、どんな状態?
↓
③その状態になると、どんな支障が出る?
↓
④本当はどうしたい?
「最終レベルの手前」の症状や状態をふりかえる
たいていは、最終レベルの体調不良になる前に、いろいろな体や心のサインがあったはず。
そこを見逃してしまうために、いつの間にか最悪の状態になってしまう。
それを避けるためには、「その前に、なんか違和感やしんどいことはなかったかな」とふりかえってみる必要がある。
私の場合は、
眠い、集中力がなくなる、イライラする、食欲がなくなる、ため息をつく、声が小さくなる、呼吸が浅くなる、起きていることが辛い、首が痛い、足首が痛い など
とにかく、思いつくことは全部書き出してみる
体調不良とともに、ほかに、どんな変化があったのか?
思いつきのままに書いた「体調不良の状態」とともに、
ほかに、変化していることはないだろうか。
私の場合は、「体のバランスの変化」と「筆記の字」
に現れ、それは「体の痛みの箇所」によって変化していた。
私の場合は、以下のように「体の痛みの箇所」が変化する。
- 右腰と右手首に痛みと動きづらさが生じる
- 左腰、モモなどの下半身に負荷がかかってくる
- 左の首や左の股関節が痛くなる
それらとともに、
- 疲れを感じる
- 呼吸が浅くなる
- 集中力が低下する
といった二次的な状態が生まれるらしい。
私は、体の部位の痛みやコリ・張りに注目したが、
人によっては、「心の状態」「人への関わり方」「食欲のあり方」など、尺度を変えた方がいい場合もある。どの尺度にするかは、「いつも悩まされている変化」に注目してみると選びやすいかもしれない。
体調不良を、さらに加速させる要因を見つける
最初に書いたように、
本当は「回復も遅いし、辛いし、やりたいことができないので避けたい」ので、
体調不良を「もっと体調悪くなれ〜」と助けてしまっている
「できごと」と「対応方法」を見つける。
私の場合は、
- 寒さ
- 座位のバランス
- 気持ちのバランス
そして、それらのできごとをゆるめる対応方法は、
- 体を温める
- マッサージ、横になる
- 好きなことをする、ストレス発散
体調不良にコントロールされる→体調をコントロールするへ
正直にいうと、このチャートをつくって携帯していたのにも関わらず、体調を崩すという結果になった私。というのも、これをつくったのは、8年前のことで、最近は、このチャートをどこかに失くしてしまっていた。
ここで大切なことは、チャートをつくることが目的ではなく、自身の体調をコントロールできるということに気づくことだ。体調不良さんに、自分をコントロールされてしまうのではなく、サインを感じ取るセンサーを持っておくことが何より大事。そのセンサーを持つために、あえて書き出したり、図式化したりするということだ。ちなみに、自分で書かなくても、家族や友人に話すだけでも、頭で整理でき、他人にも知ってもらうこともできる。その方が一石二鳥かもしれない。
気ままな人生や生活を送るためにも、歳をとるごとに必ずやってくる、体調の変化にも対応できるようになるといいかもしれない。
- 体調不良の最悪レベルを見つける
- 本当はどうなってほしいか?を忘れずに
- 「最悪レベルの手前」の状態を思いつくままに書く
- 体調不良とともに、ほかに、どんな変化があったか考える
- 体調不良を助けてしまうできごと・対応方法を考える