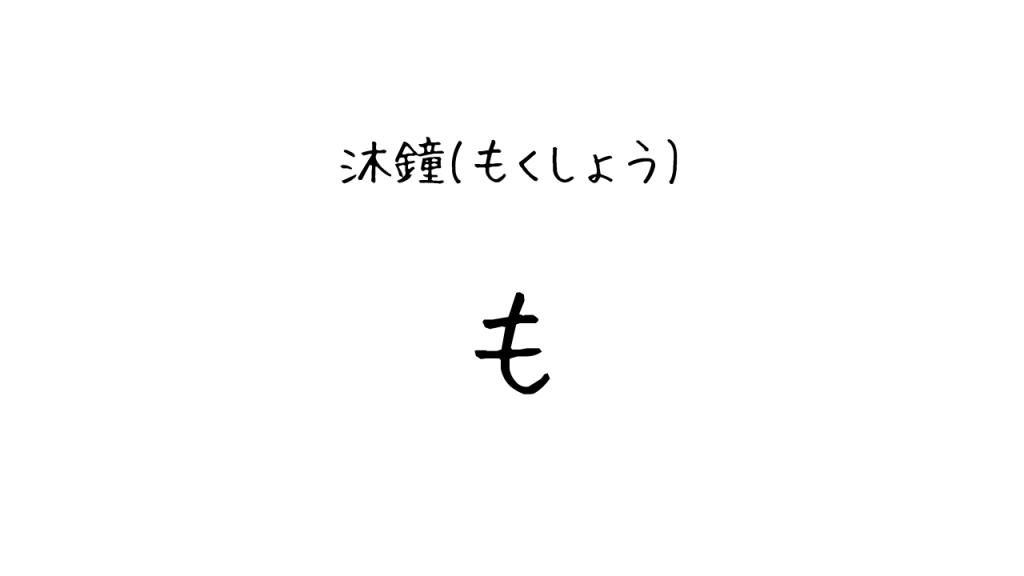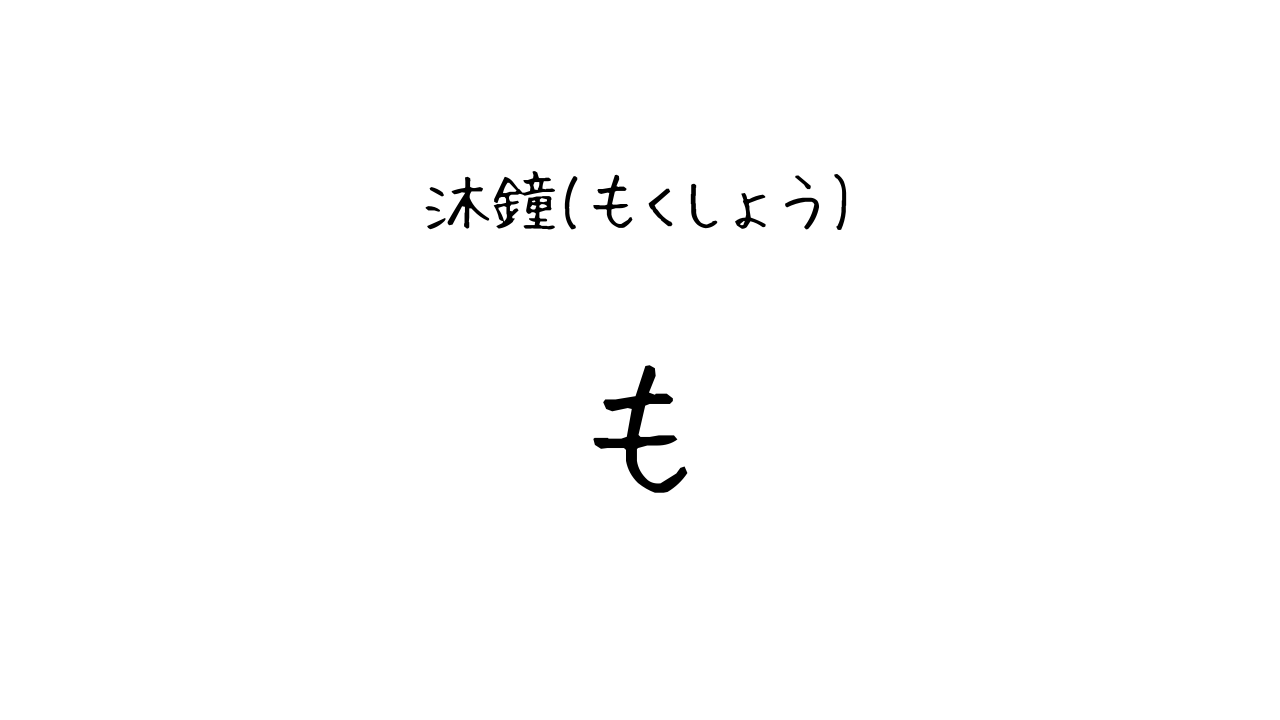目標というものがなければいけないのか?と疑問に思っていたことがあった。これから世の中がどうなっていくかわからないのに、目標なんて立てられるか!と見えない敵に怒っていたときがあった。見えない敵とは、社会の中の一見して見えない枠みたいなものだ。例えば、学校の先生や親の監視が強い中で、「もっといろいろなことに挑戦しなさい」と言われても心が縮んで冒険はできない。
障害者の世界も似たような枠がある。グループホームや家事や身体介助のサービスなどを利用するとき、その申請時に「目標立て」が必要になる。その目標立ては、相談支援員という名の専門家が行うが、福祉サービスという狭い枠組みの中で、立てる目標ってなんだろうかと疑問に思うときがある。間違った方向にいくと、「本人さんがダイエットするために、毎週月曜日にデイサービスに通って運動をする」と、相談員が決めてしまう場合が出てくる。たとえ、本人が考えたとしても、だれからも見られていなければ「やっぱやめよう」「このデイサービスは面白くないから、公民館の体育館で運動しよう」とか、すぐに変えることができる。公の資料に目標立てしてしまうと、さらに枠組みを作ってしまうような気がしてならない。
ある朝に、土壇場で有名な団体がキャンセルになり、その団体の代わりに沐鐘(もくしょう)という詩を大勢の観客の前でうたわないといけなくなった夢を見る。しかも、だれも助けてくれる人がいない様子だった。でも、私は周りが非協力的な中でも、夢中になってやっている。詩の中の漢字へのルビ振りや照明への指示まで一人でやらないといけないくらい大変だったが、朝6時に目が覚めたとき、そういうことかと考え深かった。
夢の中の私は、自分の思うがままに夢中になってやっていた。周りがどう思うかを考える必要がなくなったとき、静かな時間が流れて、目の前のことに集中できるようになるのかもしれない。詩のタイトルの「沐鐘(もくしょう)」という言葉は、辞書にはない作った言葉だが、静かな空間で、力強く鐘が鳴るイメージがある。
ときどき、だれかに鐘の鳴らし方は教えてもらうかもしれないが、自分で鐘を打っていく。静かな空間だと、自分の鐘を聞き返しやすいので、今度はこうやって鳴らしてみようと自分でわかったりもするだろう。
目標は、本来、自分のために立てるものであって、他人が口を挟むことはするものではないはずだ。他人のアドバイスを聞いて、参考にするときもあったり、じゃあ一緒にやってほしいと思ったりするときもある。そのときに、他人の手を借りたらいいのだ。
そして、目標のイメージが湧かなかった場合、きっと枠組みが頭から離れないからだろう。目の前の景色を大きく広げたら、自分の鐘を鳴らして音を聞き返しながら、一番いい音を出せるようになりたいと思うだろう。