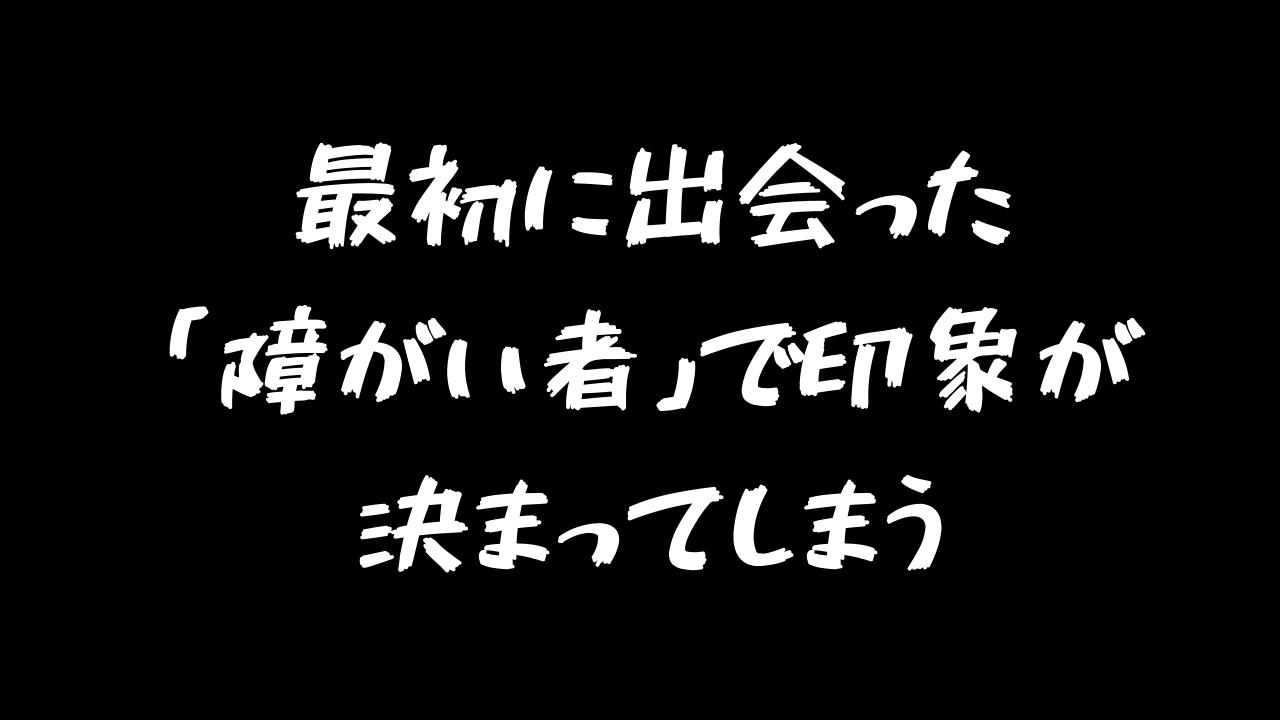「障がい」とはなにか 第2回
「障がい」とはなにか 第2回
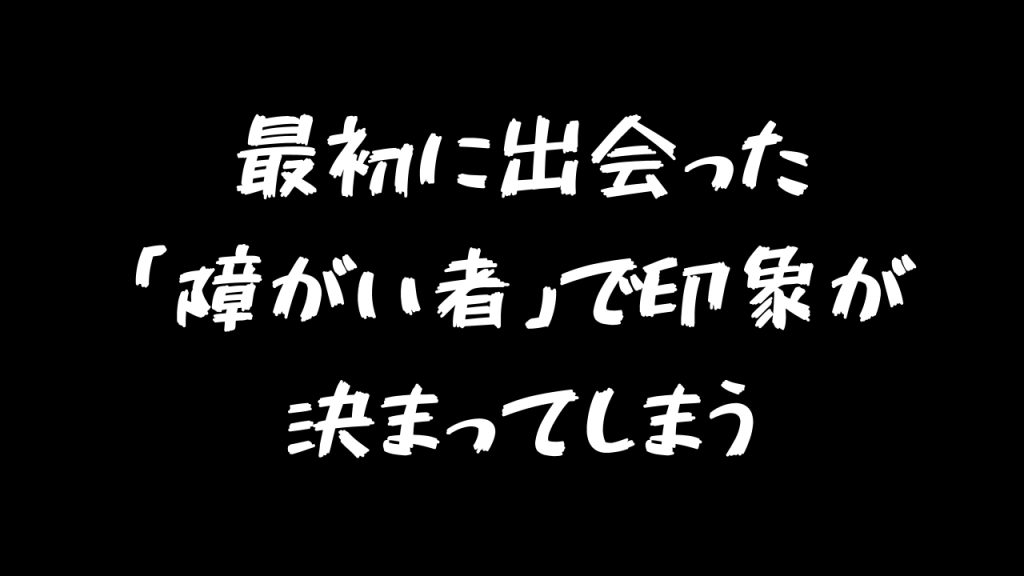
10年ほど講演活動をしてきた中で、「障がい者とどうやって関わったらいいのか」わからない人が多いことがわかった。特に、「道端で車いすの人が段差を乗り越えられずにいた場合、どうすればいいのですか。」といった質問が、小・中・高校生だけでなく、大学生や大人から必ず出てくる。よくよく聞いてみると、過去に勇気を振り絞って「手伝いますか」と声をかけたら怒鳴られてしまった人や、気になっても声をかけられなかった人、飲食店でバイトしていた時に車いすの人を見かけて、どんなお手伝いをしたらいいのか迷っていた人など、思い思いのエピソードがあることを知った。
私は、「道端で地図を広げながら困っていそうな人を見かけた時に、声をかけてみようかなと思ってかけてみるのと同じです。」と答えるようにしている。困っていたら「この場所に行くにはどうしたら良いですか」と聞かれるだろうし、大丈夫であればノープロブレムと答えるだろう。用が済めば、じゃあ!とその場から立ち去ればよい。
たしかに、障がい者側からしてみると、自分が障がい者であることや、ひとりでできないことに悔しさと情けなさを持っていれば、「お手伝いしますか」の一言で傷つくかもしれない。一方で、障がいがない人から見れば、普段から接したことのない人にとっては声をかけること自体に勇気がいることであり、そこで出会った障がい者の印象は強く残るだろう。悪いイメージを最初に持てば、声をかけることさえ躊躇してしまうだろうし、良い出会いをしていれば、次の機会に他の障がい者に出会っても話しかけやすくなるかもしれない。
誰もが一人ひとり違う性格を持っていることはわかっているはずなのに、最初に出会ったひとりの障がい者で「みんなそうなのかな」と印象付けてしまうようだ。
そういう私も、「健常者はなんでもできる人だ」という見方をしばらくの間していた。なぜなら、養護学校(特別支援学校:障害者が通う学校)の寄宿舎での生活で、先生たちから「一人でなんでもできてから自立できるものだ」と教わってきたからである。ところが、大人になってみると、周りの人たちは「これは面倒だからやりたくない」と自然に言っているし、お酒に酔いつぶれて記憶がないまま家に帰って玄関に寝たことがある人もいたし、いろいろ助けてもらいながらいきていることを知った。一人でできてからじゃないと、社会に出られないと言われ続けてきたのに、誰も完璧に生きてないじゃんと衝撃を受けたのである。少なからず、「障がい者」も思い込みを社会から刷り込まれてきたと言ってもいいだろう。
お互いに、初めてわかる、誤解のもと(五七五の俳句)
最初の衝撃は、どうしてもインパクトが強い。
しかし、そこから一歩進んで考えられるのが、人間ってもんだ。(つづく)