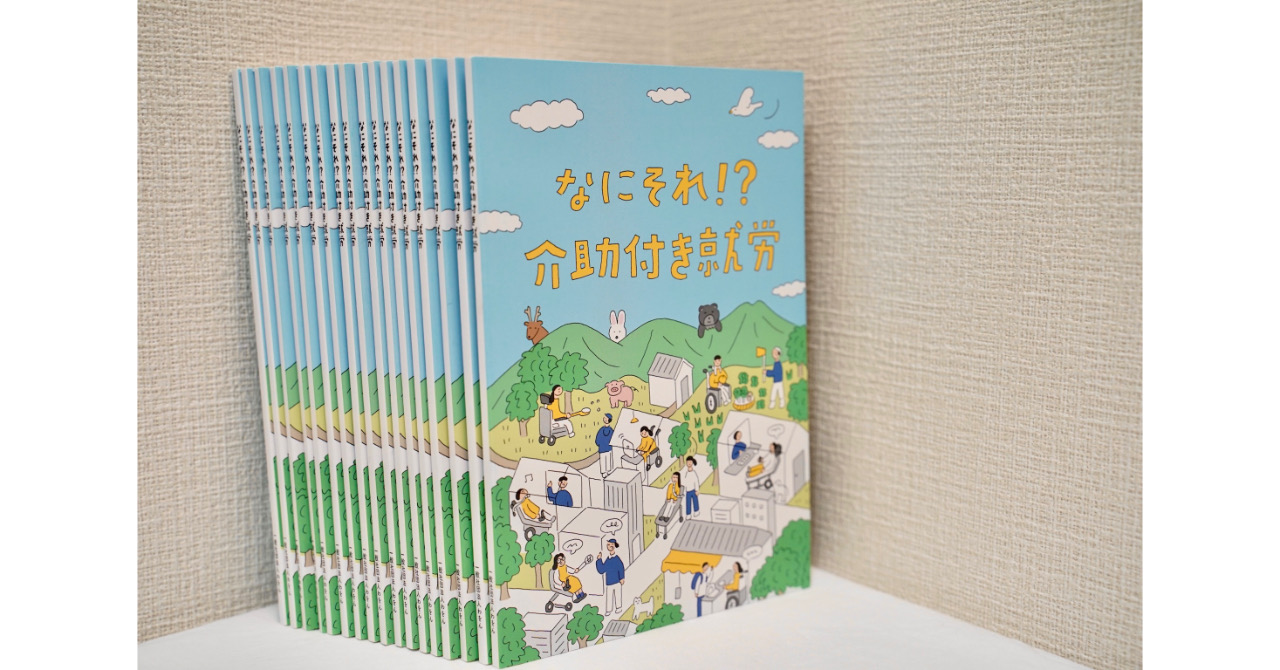「働きたいけれど、自分は介助が必要だから働けない……。」
と、働きたい思いはあるのに、あきらめてしまう障害者の方、
「私の子は、介助が必要でなにもできないから働けるわけがない。」
と、自分の子どもに障害があるからとあきらめている親御さん、
「重度の障害がある生徒の進路は、福祉サービスの就労支援しかない。」
と、今の社会を基準にして考えてしまう先生方、
「電動車椅子で、介助も必要?うちでは雇えないよ。」
と、重度障害という側面だけの判断をされてきた企業の方々、
どのかたの思いも、社会の限界だけであきらめてしまっています。
私は、働きたいと思って、何年も就職活動をしてきましたが、ずっと「介助が必要」ということが引っかかり、企業から断られてきました。
健常者でもそんなうまくいかないよ?ーーそんな声が上がってきそうですが、電動車椅子というワードだけで断られたり、使えるトイレがあるかどうか気にしたり、介助なしだったら2、3時間ならギリギリ働けるかもと生理現象と仕事を天秤(てんびん)にかけたり、「働ける能力を評価される土俵に立ってすらいない」のが現状です。
もし、みなさんが企業にこんな理由で断られたらどうでしょう。「日本人だから、うちでは働けないよ。」「男性(もしくは女性)トイレはないからね。あとは自分で考えてね。」「子育てで休みがほしい?それだったら働けないよ。」「体力がもたないから短時間労働したいの?体力なんて鍛えたらいいでしょ。気持ちの問題だよ。」などと、「あなたの状態がおかしい」という理由で言われることは、とても納得がいきません。
社会の常識はこうだからね、という理由で、その人の人間性や能力をないことにしたり、否定したりすることはしてはいけないことです。そして、障害者だけでなく、だれもが「人間のキャパシティ(もともと持っているもの)を超えない生き方や働き方」ができるようになるべきだと思います。
女性や、子育てをしている人、病気がある人や体力がない人、なんらかの理由で長時間働けない人などが、無理をしているのだとしたら、社会はもっと変わらないといけません。その延長線上に、障害者であることで直面する課題もあると考えます。
私の周りには、働きたいと思っている障害者がたくさんいます。介助が必要だからという理由で、働きたいけれどあきらめたり、周囲から働けないと言われたり、働ける方法やその情報にたどり着かなかったり、今の社会制度では限界があったりします。
働くチャンスがあれば経験を積んで、スキルをアップしたり、障害のある人もない人も、それぞれ持っている能力を活かして協力し合えることがあったりするのに……。そういう思いを持っていたところに、一般社団法人わをんで障害当事者の支援をしている方々や、同じように働きたいと思っている同志が、あるハンドブックを作成するということを知り、参加しました。
それが「なにそれ!?介助付き就労」というハンドブックです。

詳しくは、一般社団法人わをんのNote記事(ハンドブック「なにそれ!?介助付き就労」ができました!)をご覧ください。
人間には、本当はキャパ(キャパシティ:もともと持っている体、能力など)に限りがあります。もちろん、人それぞれ得意・不得意や、できる量や範囲は違うでしょう。
それが「他の人よりも、私はできない」ということに引け目を感じ、私たちは気持ちを縮こませてしまいます。でも、今はいろいろな機械があり、パソコンがあり、インターネットがあり、そしていろいろな知恵があります。ありとあらゆる方法を使えば、それぞれが持っている能力をうまく、無理なく発揮できるのではないでしょうか。
このハンドブックの内容は、介助が日常的に必要な身体障害者の就労のあり方を柔軟に広げるための、具体的な実態や方法、考え方が書かれています。
ぜひ、すべて無料でPDFで読めますので、ご覧いただけると嬉しいです。
PDFのリンクです→なにそれ?!介助付き就労
よろしくお願いいたします。