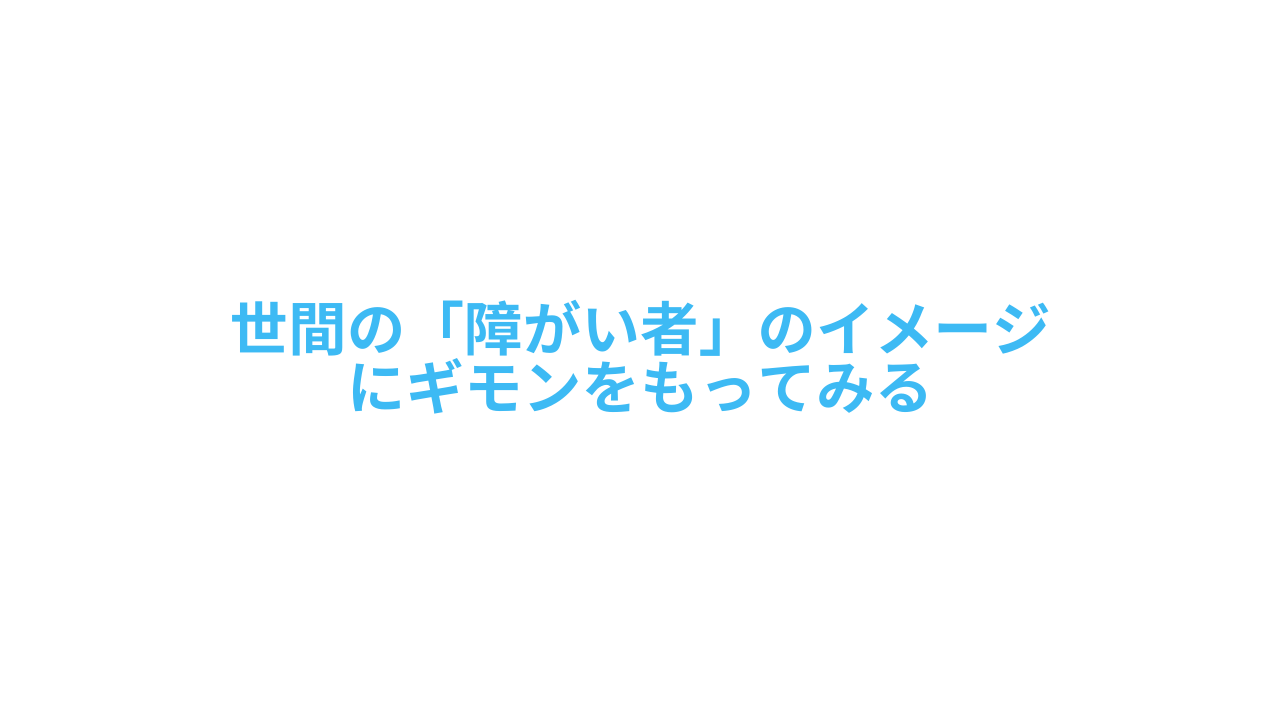今日から何回シリーズかわからないが(笑)、おそらく7回ほどで同じテーマについて書いてみたいと思う。テーマは「障がいとはなにか?」だ。
「障がい」とはなにか 第1回
「障がい」とはなにか 第1回
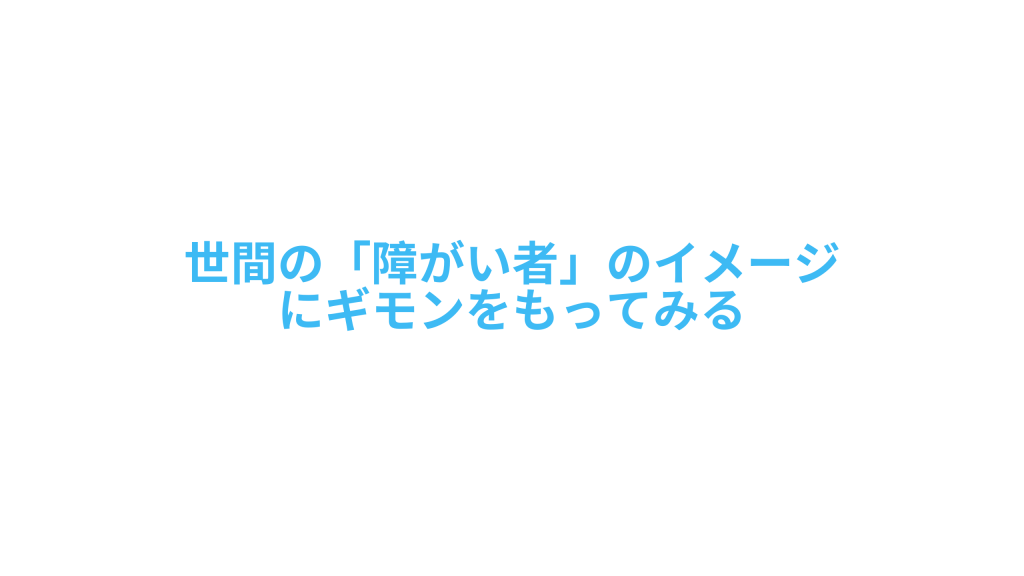
世の中の人も、私も「障がい者」という言葉に惑わされていないだろうか。30歳を越えた私は、そのギモンを放っておくことはできない気がしていた。これまでの人生の私の心境の変化はめまぐるしかった。
「自分は他人とは違うという孤独感に陥った」10代
「『障がい者』という見られ方に慣れてきた」20代
「自分を『障がい者』と思うことに違和感を感じ始めた」30歳手前
「世の中の『障がい者観』を見直さないとならないと感じ始めた」30歳過ぎ
「シンプルな生活の中に答えがあるはずと気張っていた肩を下ろす」今の私
このテーマの中で、なんとなく整理できればいいなと淡い期待を抱いている。
今から8年前にさかのぼる。ある大学の理学療法学科約90名の学生さんの前で、いつもより変わった自己紹介をした。後ろの席に座っている学生が、前の学生の肩の間に顔を出してこちらを見ようとしている。「みなさん、こんにちは。私は電動車いすに乗っています。後ろの方、見えるでしょうか。黒いシートに紫のメタルフレーム。札幌の地下で人の波をかいくぐってスピードを出すのが大好きです。最近は、車いすを『ポルシェ』のように乗りこなすことで有名です。」
一般的に車いすには、けがをした人、病気、おじいちゃん、おばあちゃん…というイメージがある。ドラマや映画、24時間テレビでは、「障がい」は「乗り越えるもの」というイメージが印象的だ。「障がいを克服する姿」を見て、感動したり、自身の至らなさを痛感して「私も頑張ろう」と思ったりする。
最近は、少し明るいイメージが加わり、車いすユーザーのアスリートやモデルなどの活躍がメディアに出てきた。2020年のオリンピック・パラリンピックなどをきっかけに、ますます見る機会が増えてきた気がする。悲しくて暗い話題ではなく、楽しくて明るい話題の方が、自然に気持ちの中に入りやすい。
車いすユーザーの私は、「障がい」のことについて講演するとき、明るい話題から始めるようにしていた。格好良く、大胆に自己紹介をし、「障がい」を身近に感じてもらうための作戦であった。
しかし、いつまでもこれでいいのかとギモンに思っていた。なにごとも、知らない人に伝えるときには、言葉や写真、映像などを巧みに使うのは必要なことである。視聴者の感情に響くように、発信者はあの手この手を使っている。そのために、本来はものごとの一番伝えたい本質を知ってもらうはずだったのに、いつの間にか視聴者の中に眠っていた感情のいいなりになってしまっている気がした。24時間テレビは、感動を求めている人や障がい者のほんの一握りの姿を見て終わってしまっている人が多いために、何かに挑戦するというスタイルのままで長寿番組になっている(と私は思う。)ように。
そこにいつまでも立ち止まっている私も、なにか違うかもしれないと思う今日この頃。世間の「障がい者」のイメージがなぜ続いているのかを、紐解いていきながら、もっとシンプルに考えられないかと探してみたいと思う。(つづく)