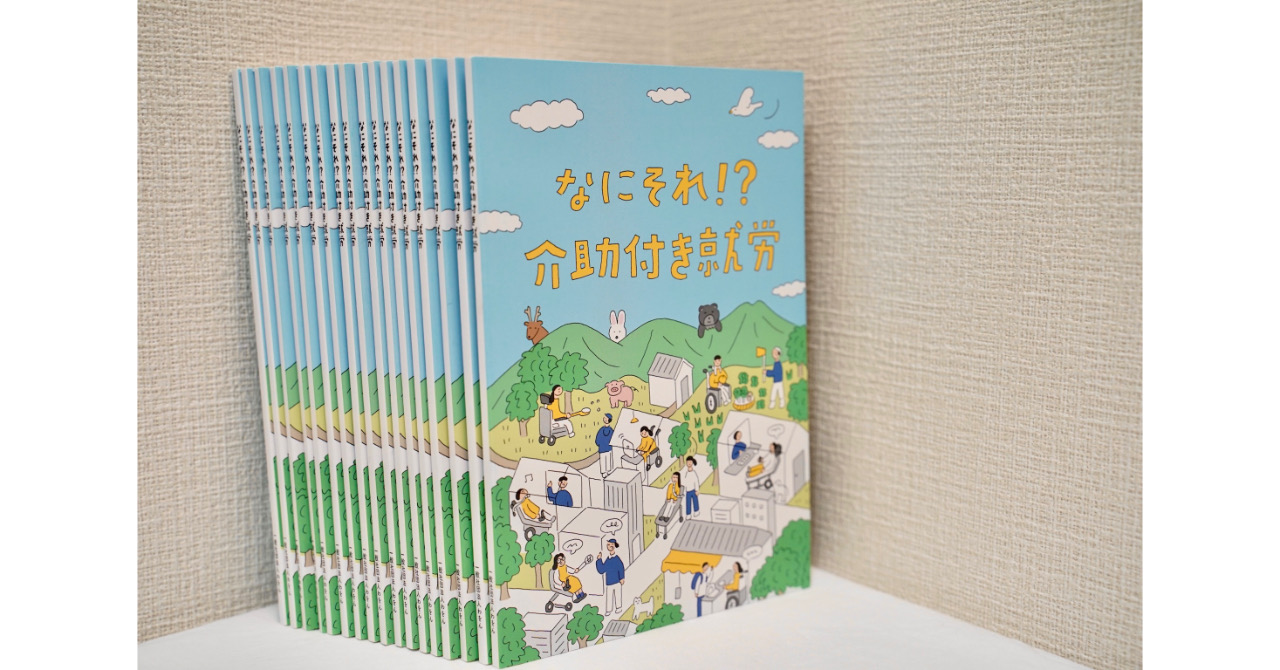別の記事にも挙げましたが、介助が必要な障害者の就労の現状と、進むべき未来について書かれたハンドブックができました。
タイトルは、「なにそれ!?介助付き就労」。
日常的に介助が必要であるほど、私たちの存在が社会に知られにくいのが今の現状です。私たちがどういう生活をしているのか?具体的には、ヘルパーさんを利用しながらの「自立生活」について、まだまだ社会には知られていないと思います。
そもそも「自立生活」とはなんでしょうか。
世の中には「何もかも一人でできること」と考えている人が多いです。障害のある私たちから発信している「自立生活」の言葉の意味は、「社会のあらゆる資源や人の手を借りながら、自分の意思で生活をつくり上げること」です。実は、障害があろうとなかろうと、だれもが、いろいろなものやサービス、人の手を借りて生きていると言えます。そして、だれもが、100%の健康体でいられるという保障はなく、だからこそそこを補うものが社会的に必要だと考えるのです。そのことに直接気がついているのは、特に、なんらかの理由で病気や障害がある人。たとえ、健康体でなくなっても、自分の生活が変わってしまったり、諦めてしまったりしないように、社会をいい環境に整えていく必要があるのです。
その一つに、働くことについて、介助が必要な障害者が今、どのような状況に置かれているのか、どのように社会が変わっていくべきかが手に取るようにわかるよう、ハンドブックを作成しました。
私は、この取り組みに関わらせていただいて、本当に良かったと思っています。このハンドブックの内容や編集について、他の障害当事者や介助経験のあるメンバーと、たくさんの時間を重ねて話し合ってきました。
まずは、「介助が必要な障害者の就労についてハンドブックにするにあたって、『働ける・働けない障害者』という区別やレッテルを貼るようなことはしたくないし、『働いていない』からと言って、いろいろな事情や思いがある。このハンドブックは、あくまでも『働きたいと思った障害者も働けるという選択肢』を増やすためのものだよね」、という認識を共有しました。社会が「能力がある者・ない者」に分けてしまっている中、障害者の中でも、そういった同じような差別をしてはならないということを気をつけていました。
それに、いろいろな働き方があるということも、見逃してしまいそうなことです。働く=フルタイムではなく、短時間の労働やその時期だけの集中的な働き方、さらに、ものやデザイン、発想までも売ることもできるし、地域やだれかに貢献するボランティアもあります。そこから、働き方が広がったり、長い時間働けるようになったりします。
本当はいろいろな可能性があるのに、その可能性の足を引っ張っているのが、今の社会制度や、人々の認識、あきらめだったりするのです。それらのことを現状とともに、このハンドブックであらわしています。
ハンドブックの内容は、PDFで無料で見ることができます!
ぜひご覧ください。