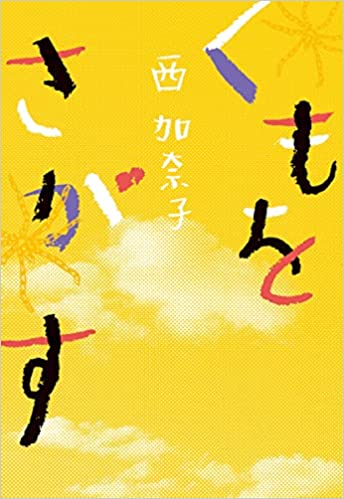読み終わったあと、私は余韻に浸りたい、いや浸らないと損をする、と思った。
こんなに弱っている自分の体を、
内側から見つめることが出来るのは、私だけなのだ。
p100
西加奈子さんは、カナダで乳がんが発覚し、「ただただ治療をする」毎日を送った。「闘病」とか、「病をやっつける」とかそういう言葉を使いたくない、ただ事実としてあるだけで、治療を進めていくという表現を使っている。私は、この本を読んでいるとき、私自身の体のことを考えていた。小説のようなフィクションではない、まぎれもなくノンフィクションであり続けた。出版を考えて書いたのではなく、ただただ西加奈子さんが追い続けて書き続けた。だからこそ、読者としての私は、乳がんのことや自分の体のことをもっと考えよう、と思った。
カナダで治療を受けたということも、興味を持った。それは予想を遥かに超えた。医療体制のことだけでなく、むしろ、その他の多くのことが、西加奈子さんの自身との対峙を支えてくれたのだと思う。例えば、食事は、Meal Trainという友人などの周りの人の手作り料理を食べるという方法がとても助かったと西加奈子さんは話していた。私もとても大切だと思った。カナダでは、気兼ねなく友人が助け合う風潮があり、助け合いのフットワークの軽さがあるようだ。それは、カナダの広い土地でのびのび暮らすことで、日本とはまた別の優しさやおおらかさが出てくるのかもしれない。
「あなたの体のボスは、あなたやねんから。」
p98
私は、「自分は、自分の体の管理人だ」と思っている。だから、カナダの医者や看護師が言っていたこの言葉は、本当にその通りだと思った。
西加奈子さんは、抗がん剤治療をしているとき、漢方薬治療をしないようにと言われたあと、これまでずっと自分の体を支えてくれた漢方はやめたくないと医者に話すと、「そうなんや、オッケー!」「もちろん、決めるのはカナコやで。」と案外あっさり返されたという。
「あなたの体のボスは、あなたやねんから。」というカナダの医者や看護師の言葉。残念ながら、私は日本で言われたことはなかった。障害のある私は、いつも自分の体と向き合わないといけない、というより、嫌でも向き合わざるを得ない。そのような体と真摯に向き合う姿は、かっこ良くもなんともない。生活するために、生きるためにすることの一部に過ぎない。そういう意味で、西加奈子さんの「ただただ治療する」という感覚に近いと思う。
「ただただ治療する」という中に、必ず主人公がいることを、カナダでは思い出させてくれるのだと思った。病院の看護師の中に、自身も乳がんを患い乳房を切除した人がいて、「看護師も乳がん患者の当事者」として、切除部分を見せてくれたり、経験を教えてくれるという。だれもが主人公として、他のだれかを助けようとする。西加奈子さんも、いろいろな乳がん経験者の友人に支えられながら、当事者となっていく。
すべての過程が西加奈子さんの言葉によって綴られている。
迷いも、幸せも、何もかも詰まった一冊だった。