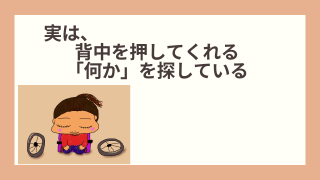いつも気になっていた、あの小さな空洞に入ってみたい。
三船幸一は、いつも心に決めていた。それは、庶民的なデパートの一階にあたる路面に面したところにある。デパートと言えるほどのお店はないどころか、シャッターで閉められている店が大半だ。いつも目にするが、デパートに用事などはないから、そのついでに見るのではない。JRの駅が近いから、駅を利用するたびに、その空洞の横を通り過ぎるのだ。
その空洞の上に「古書店 坂之上」と書いてある。
宝くじ売り場の2個分くらいしかない小さな空洞。そこには、天井と壁一面に本がぎっしり詰まっていて、真ん中にあるやせ細った棚は正面を向いてお客を出迎えている。まるで遠くから見たら「間」という字に見える。しかも、店の奥には、本棚に収まらず平積みになった本が自動販売機ほどの高さまで積み上がっている。
三船は、いつも横目で見ながら通り過ぎていた。
駅に向かう時は左目で、駅から家に帰る時は右目で。ただの通り道でしかないと無意識に思っているせいか、足を止めるのが億劫だった。足を止めたら最後、本を探す行動に移らないといけない気がする。おまけに、店の奥で何かを読んでいる店主と目が合ってしまったら、という想像まで膨らんでしまっていた。その妄想までもが恥ずかしく、三船は何も考えていないふりをし続けてきた。
三船は「古本屋に立ち寄りたい」という意志を示さなければならなかった。
そうしなければ、きっと、一生立ち寄ることはないだろう。
なぜなら、三船は、常に他人に押してもらって移動しているからである。勇気がないからという理由で背中を押してもらうのではない。押される“もの”は、リクライニング機能があって、背を倒すことのできる車いすである。三船の身長は180cmもあるため、体型は痩せていても、身長分以上もある大きい車いすだ。
むろん、“もの”と言ったら三船に怒られる。
車いすは、三船にとって足だからだ。
「三船さん、どこか寄って行きますか?」
車いすを押していた塚本は、なぜか古書店を過ぎたところで、足を止めて、三船に聞いてきた。塚本は経済学部の大学生で、三船のところで働いてまだ半年しか経っていないが、三船は30も年下である彼の腕を認めている。
三船は彼の目をじっと見る。
塚本は車いすの後ろに差してあったプラスチックの下敷きを、すかさず出してきた。塚本は三船と向かい合い、透明の下敷きを三船の顔の前に持っていく。ひらがなの五十音表がマッキーペンで書いてある。文字の隙間から透明な下敷きの向こうにある、三船の視線のありかを探す。
三船は、塚本をじっと見たものの、どうしてこのタイミングで聞くのかと内心ドギマギしていた。なんせ、全身どころか、顔の表情まで動かせられないから、三船の焦りぶりは塚本には伝わらない。三船は、若造に焦りがバレなくて良かったと思いつつ、安心している暇もなく、真剣な眼差しで自分の視線を追っている塚本に応え始める。
「か」
塚本は視線で止まったところを指差して、声に出す。
「え」
三船にとって、視線をひらがな文字に合わせて動かすことはたやすい。
でも、心がついていかないことがある。こんなに言葉が難しいなんて思ってもみなかった、と三船は今の体になりつつあるときに感じ始めた。しかも、自分は国語を教えていたのだから、当時は鼻で笑ってしまった。この方法を受け入れるまでに時間がかかった。
「あぇ……、三船さん、次は?」
若造が困っていることに気がつき、三船は我に帰った。
「帰りますか?」と、塚本はいつものように自然な口調で先回りして答えた。機械的な言い方でもなく、威圧的な声色でもない、優しくて、自然な口調だ。三船は、yesと合図しようか迷った。これもウィンク一つでできることだ。
三船は視線の行き場を失っていると、
「俺ね、あの、たまに思うんですよ。なんか、三船さんって、ふらっとどっかに寄りたいと思うこと、ないんかなぁって。んー、俺だったら?バイド帰りにゲーセンに寄っちゃいますね。」
三船は、塚本が恥ずかしそうに地面に視線を落として話しているのに気がついた。
「でも、車いす押されてたら、あ、ちょ、ちょっと、ここ寄るわっ止まって!なんて、言う暇ないっていうか……。タイミング失いません?」
三船は、タイミングか……いいこと言うな、
と塚本を心の底から褒めた。
塚本は、じっと見られていることに気がつき、もう一度「帰ります?」と尋ねた。
三船はウィンクをして笑ってみせた。
頬の筋肉さえも重力に負けて動かないが、かすかにビクビク目の下の筋肉が震えた。
三船にとっては、筋肉を震わそうとした。
「三船さん、もしかして、俺のこと、バカにしてますぅ?」
塚本はそう言いながら、パーカーのポケットに手を突っ込み、わざと大回りして車いすの背後に回った。
ブレーキを外す音とともに、塚本のヘルパーモードのスイッチも入った。
「行きますね!」という若造の声。
三船は、夕暮れの空に向かって、2回、密かにウィンクをした。