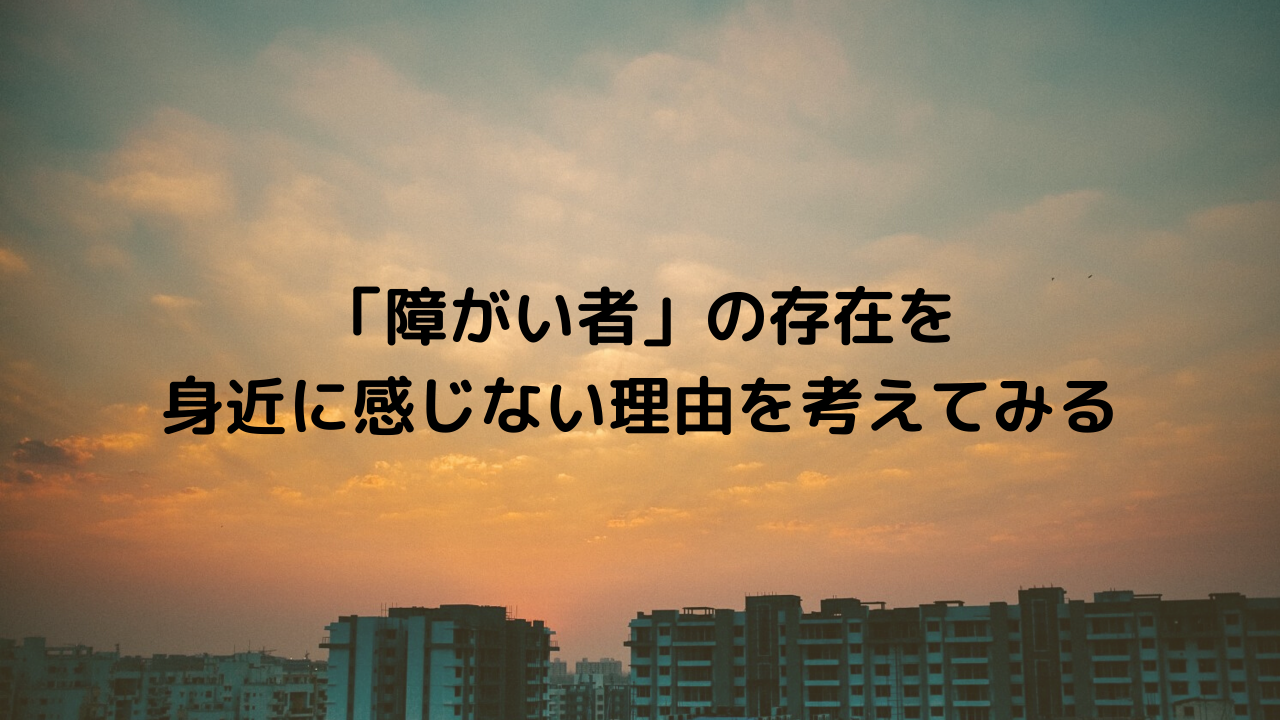「障がい」とはなにか 第3回
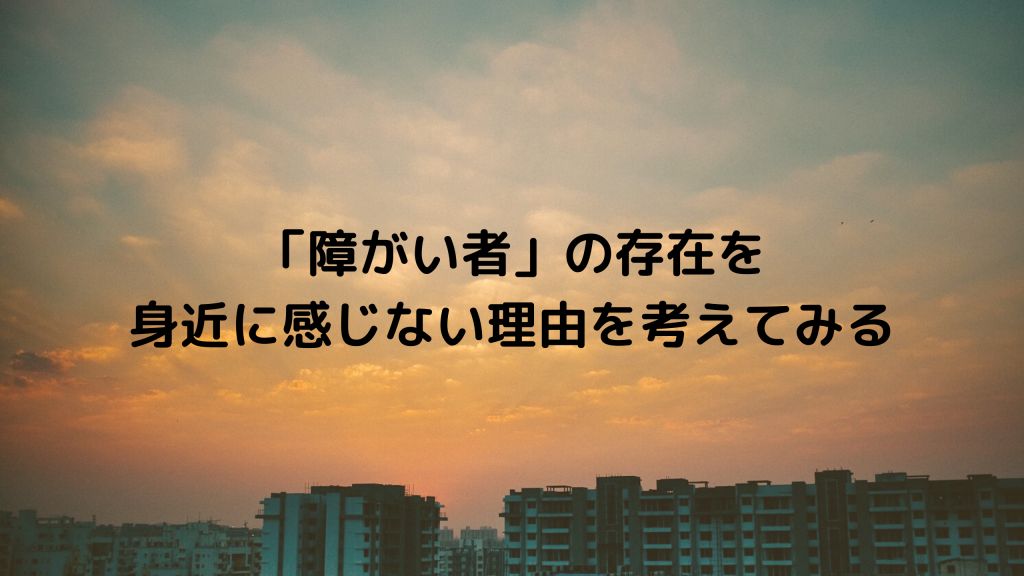
実際に、100名近くの理学療法学科の学生に、「あなたの友人に、障がい者や車いすユーザーはいますか?」と聞くと、手を挙げるのは2名ほどだ。それも、小学生の時に一緒の教室にいた、という記憶しかない人もいた。「障がい者」のイメージがメディアに影響されてしまうのも納得できる。
「障がい者」と言われている人々やその家族の多くは、時に自分のことで精いっぱいで、周りに心を開けない経験をする。なぜなら、「障がい」と向き合うのは誰でも、その本人でさえも初めてだからだ。足が不自由になり車いすを使うことになれば、階段を上るために知恵を絞らなくてはならない。学校や職場の階段が「障がい」になり、学校生活も仕事の機会もなくなる。人生を歩んでいた先に「障がい」が立ちはだかるのだ。
だから、「障がい者」にとっては、選ぶことのできる学校や職場は限られていて、環境が整っているところに、「障がい者」だけが集まってしまう状況になっている。「障がい者」側が普通に暮らしていきたいという思いを曲げないようにしないと、特定の場所に止まらざるを得なくなり、より遠い存在に思われてしまう。
私は、今では、手を貸してもらいたい時は、通りすがりの人であっても声をかけるようにしている。ある日、横断歩道を渡る時に、段差が少しあったため、同じタイミングで渡る男性二人組に声をかけて、後ろから手伝ってもらいたいと声をかけた。一緒に渡りきった時に、男性から「このバッテリーってどうやって充電するんですか。」と質問された。「自宅にあるコンセントにつないで充電できるんです。」と答えると、彼らはあ~そうなんだとすっきりした顔で嬉しそうにしていた。
冷静に考えると、電気自動車や電気自転車と同じような感じなのにな〜と思うのだが、会話のきっかけだったのかもしれない。こういった何気ない会話は、一緒に教育を受けられる社会であれば、小学生のうちからできていたかもしれない。大人になってからの交流では遅すぎるのである。
もし、子どものうちから自然と交流していれば、障がいや老いること、体に変化が出ること、人間は不完全な生き物であることを、自分の身に置き換えて考えられるようになるのではないか。「障がい者に理解を!」というよりは、みんなの生きることへの不安が少しでも減っていく助けになると思う。
私には障がいのある友人がいるため、人生においてラッキーなのではないかと思うのだった。なぜなら、自分は障がい者であるかもしれないが、生まれつきということもあって(笑)、今の状態以外に、何も考えることができないからである。遊んだり、話をしたりすることで学んでいったのである。そもそも、自分以外のことは、自分の想像だけで完結することなどできないのだ。(つづく)