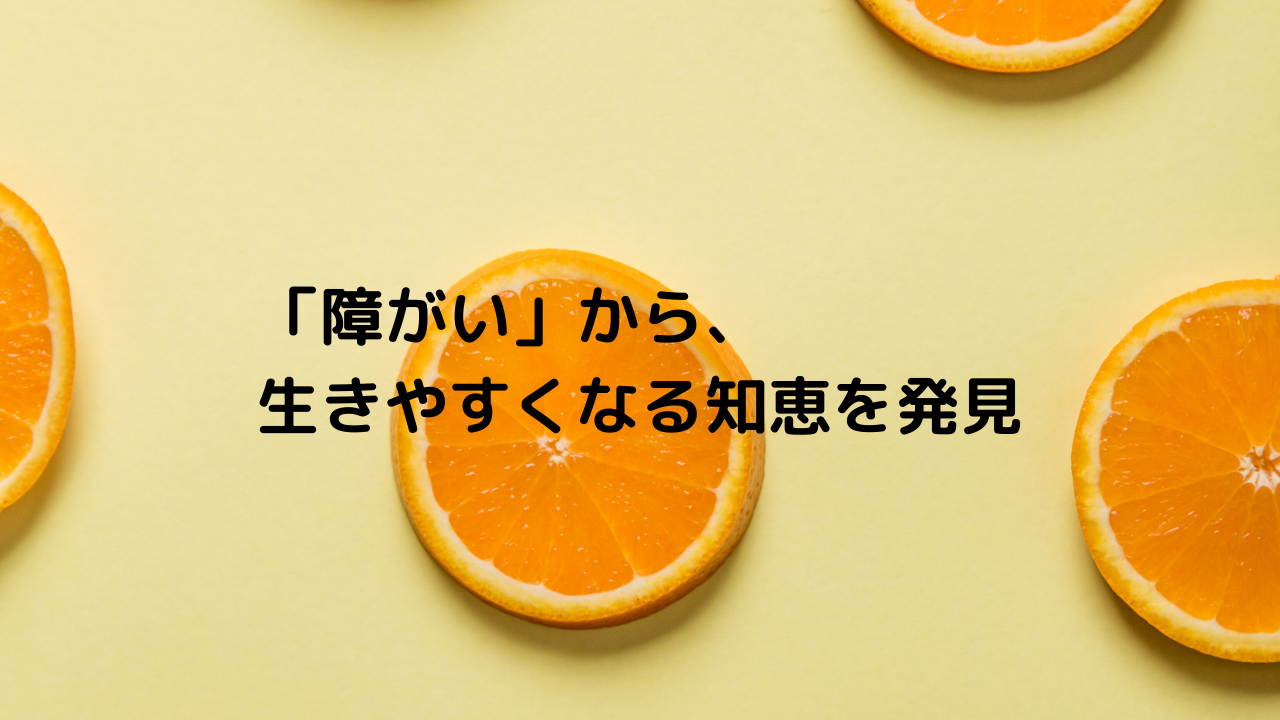「障がい」とはなにか 最終回
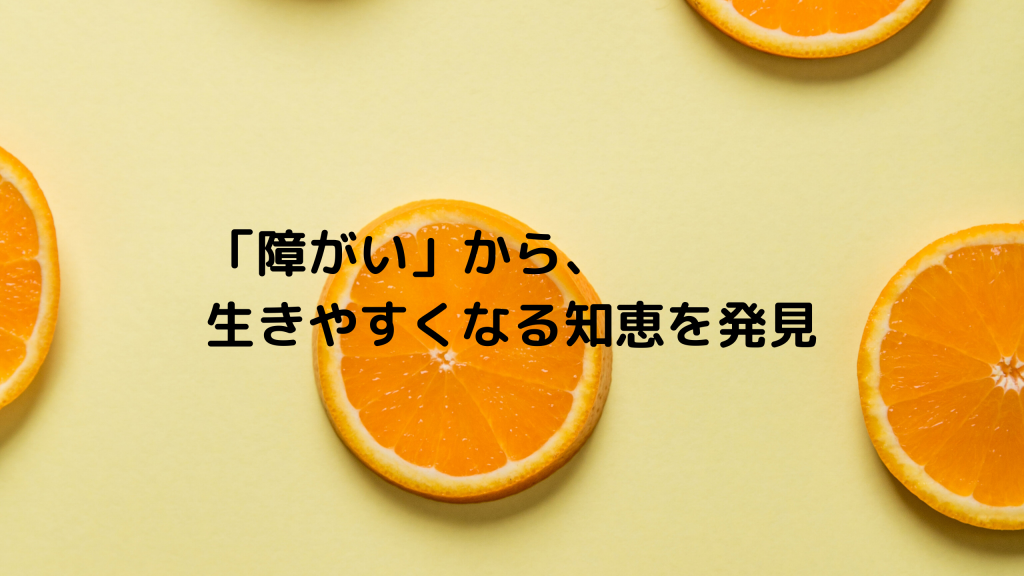
6回にわたって「障がい」について書いてきた。実を言うと、障がい、障がい、と何回も考えたくない気持ちが本音である。まず、わかっていることは、人間の体は完璧ではないということである。これを否定してしまうと、私たちの生活は少しのタイミングで崩れてしまう。それが崩れてから、環境を変えなくてはならないことに気づき、さらに、社会ももっと生きやすい仕組みを作ってほしいと切実に思うことになる。しかし、そうなってからでは、もうすでに体力も気力もなくなり、自分で何かを変えようとか、社会に伝えていこうとか、こういう生活になってほしいなどという希望を持てなくなっている。だから、私は、大多数の意見や少しの行動が必要不可欠であり、いろいろな人が自身が障害になる前に、知っておいてほしいと思っている。しかも、小学生のうちから、楽しく、学べる仕組みをつくることができたら最高である!
障がい者あるあるを一つお伝えすると、私は障がいのある友人と関わりがあるとき、お互いの障がい名をまったく気にしない。それどころか、障がい名すらもわからないことのほうが多い。なぜなら、障がい名ではなく、「どんなことに困るか」「どんな手助けが必要か」を知るだけでいいからである。自身でコップを持つことができないなら、飲食店でご飯を食べに行くときに、ストローを店員さんに頼む。広いトイレが必要だったり、トイレを済ませるまでに時間がかかったりするなら、広いトイレの場所をあらかじめ調べておくとか、トイレのときは待っているとか、するといいのである。そんなに、大きなことはないのである。
車いすユーザー同士のあるあるは、お互いの車いすの種類や会社を気にしたり、付属の道具(ペットボトルホルダーや携帯電話スタンド、アゴで動かす電動車椅子のジョイスティックなど)に関心を持ったりする。私が、今探しているのは、車いすごとカバーするレインコートで、持っているけれど、もっと薄くてコンパクトのものがほしいのだ。車いすユーザー同士の方が情報を持っていることもあるので、同じ境遇の中で情報交換することは大切である。
世の中には、私の知らないことがたくさんある。北海道ではアイヌのこと、世界中では貧困のこと、子どもに降りかかっている問題など、「目に見えていない」ことが数え切れないほどある。「内側」「外側」では見えていることはまったく違うのだと思う。むしろ、それを前提に考えないと、わかったフリになったりする。私もそうだが、深刻な話題になると、どうも自分から遠ざけたくなってしまう。深刻なことであっても(あるからこそ)、自分がまだ学べる環境にあるうちに、知っておいた方がいいことは結構あるのかもしれない。子どものうちに、優しい言葉で、いろいろな世界の状況を知っておいたほうが、「自分だけが苦しんでいる」「自分には何もできない」「自分さえ良ければいい」などと思うより、「うわー、なんかしたほうがいいかも〜」「自分も似たような思いをしたことがあるよ」と思えるかもしれない。
生きるにあたって、身を削るほど頑張っていることがあれば、それは「本当に自分の人生に必要なことなのか」、「続けたいことだが、もっと他のやり方がないか」など、「余白」を持った考え方ができると楽になると思う。
その「余白」を考える状況にあいやすいのが、おそらく、障がいのある状況なのだと思う。そのことで、日々考える力がついてくる。いきなりやることは難しいので、日ごろから「生きやすくなる知恵」をみんなで出し合う機会をつくることが大切なのかもしれない。