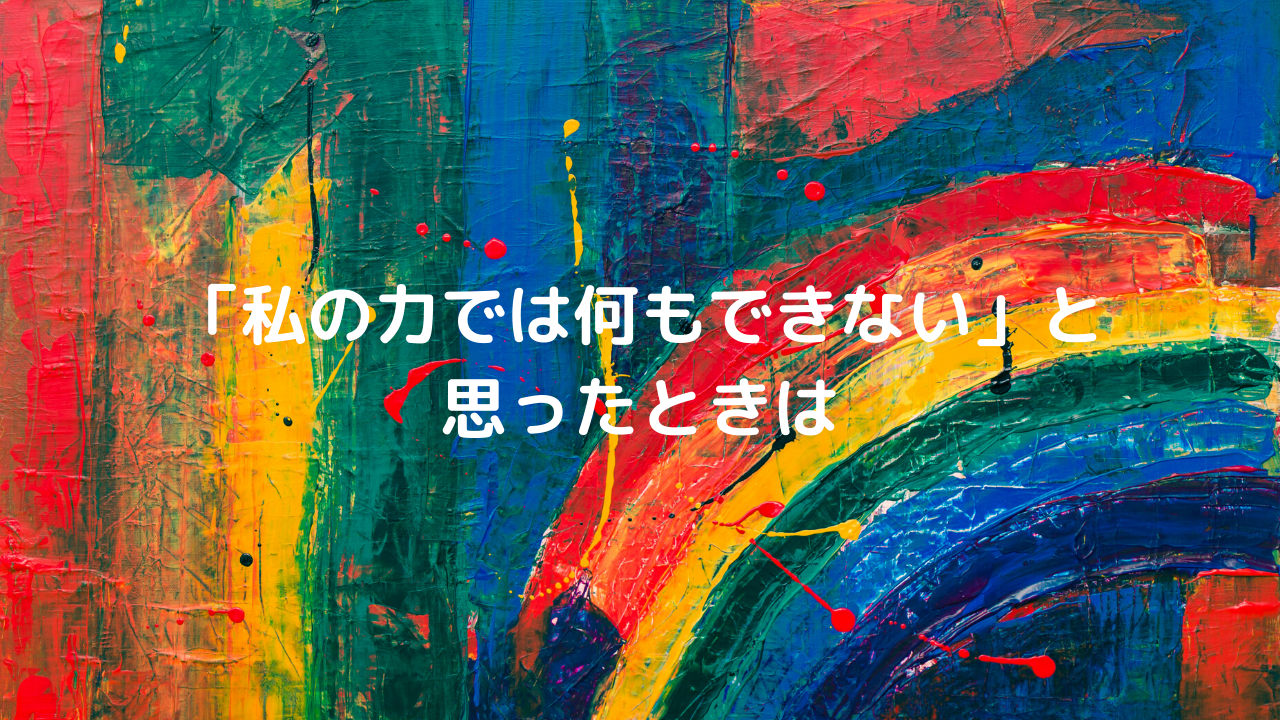私の介助に入っている大学生Yさんと、医療や福祉の問題について話をして、内容の濃い時間を過ごしました。こんな時、私は、「あぁ、学生さんを雇ってよかったな〜」と思います。最近は、私の介助をスムーズにできるようになり、時間がたっぷりできるようになったので、初めてたくさん話しました。
Yさんは助産師さんを目指して、医療系の大学に入り看護師課程で勉強しています。小学生の頃に、妹が生まれる時、出産に立ち会い、お母さんが命を誕生させる瞬間を見て、「助産師に絶対になる」と心に誓ったそうです。「この日がなければ、今の私はない」と言葉に力強さがあります。明るくてパワフルで、いつも元気づけられます。
私は、普段はのんびり暮らしたいので、あまり社会問題を人と話さない方です。だって、イライラしてしまうと体に緊張が入って固まってしまうんだもん。
しかし、今は、そうも言っていられない状況にいます。
それは、この学生さんをはじめ、色々な人が私の介助に入っている「PA制度」の仕組み(詳細は下に参照)には、新型コロナウイルスの感染予防に必要な物資などが保障されていないのです。
マスクや消毒液などは最低限必要ですが、ヘルパー事業所に配布されても、PAには支給されないことに憤りを感じています。
そのことをPAと話す時間がなかったのですが、今回は思い切って話してみました。マスクや消毒液の他に、ビニール手袋、うがい薬、手を洗う時に大量に使う水道代など経費がどんどんかかり、万が一に必要な防護服には手が届きません。お金がある人は買えばいいと思うかもしれませんが、お金に余裕がない人も同じように介助が必要です。感染予防ができる人とできない人と差ができてしまうのはおかしいことであり、その差を埋めるのが政府の役割だと思います。
「どうせ、コロナにかからないよ。大丈夫。」と思っている障害者も多いと聞きます。そう思うことが悪いのではなく、「そう思わなければ、やっていけない」状況」に置かれることがおかしいのです。
Yさんは、それを聞いて「医療や福祉に必要な物資が行き渡らないなんておかしいと思います。でも、そんなことを一人の私が言ったって変わらないような気がしています。」と言っていました。
「言わなければ、何も伝わらない。」
それは100%言えることです。
NPO法人いちご会という「障害があっても、自分で選んで、生きることを当たり前としたい」と40年以上も活動してきた団体があります。
小山内美智子さんという脳性麻痺の女性が、どんなに重い障害でも堂々と生きる社会を目指して、行政と戦ってきました。
そのいちご会の年4回発行している通信に、色々な障害者の方が自身の経験を書いていて、Yさんにその通信をじっくり読んでほしいと伝えました。
中途障害により「急にできなくなった」状況で葛藤しながらも外国へと言った女性の話や、筋肉が弱っていく病気を持ちながら行政書士をしている人の話など、どんな状況でも、可能性を切り開いて言った方の経験談がたっぷり詰まったものです。
きっと、「今の状況を変えたい」「誰かの助けになりたい」と思った時に、背中を押してくれるのは、多くの経験談に触れることなのだと思います。
私も、今も、色々な経験談に触れていきながら、力をつけないといけないなと思っています。
話終わったあと、軽やかな足取りで帰ったYさんの姿を見て、私もなんだか救われたような気がします。
※PA制度(パーソナル・アシスタンス制度)とは
介助を必要としている障害者が、介助の仕事をしたいという人と個人契約を結び、時給を払う仕組みです。介助の仕事をする人をPA(パーソナル・アシスタント)と言います。
デンマークやスウェーデン、ノルウェーなどの欧州を中心に始まり、個別のニーズ(必要なこと)に応じたサポートができるよう専属のアシスタントを雇用する考え方と制度が生まれた。北海道札幌市では、2010年にPA制度をつくり、障害者総合支援法の介護給付のうち「重度訪問介護」の支給を受けている障害者を対象に、制度運営をしている。
介助を必要としている多くの障害者は、基本的に、ヘルパーを雇っている「事業所」と契約を結んで、「事業所」の判断でヘルパーが派遣される仕組みを利用している。一方で、PA制度は、基本的に、障害のある本人がヘルパーを探し、面接をし、報酬を払う手続きを行い自分で管理する。