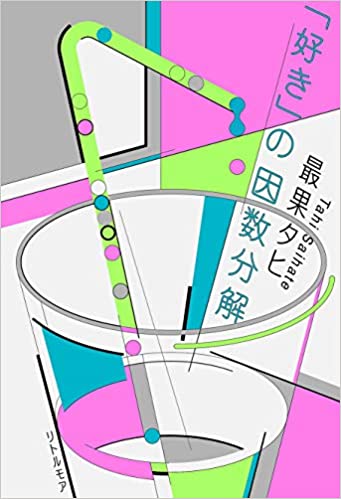何かを話そうとするとき、何かを書こうとするとき、最初の言葉を出す瞬間が一番ドキドキします。頭の中にたくさんの数えきれない言葉があって、伝えようと思っているできごとを表すための言葉を選ぶのに正解がなくて、だからこそ、どんな言葉を選んだらいいのかわからない。でも、そこで止まっていたら、何も進まないから、けっきょくは何も考えずに、スルッと言葉にしてみようとします。そうじゃなきゃ、心臓がもたないので、早死にしてしまいます。
Spotifyのラジオで、最果タヒさんの「『好き』の因数分解」について、なんとなく聞いて、ちょっと読んでみようと手に取ってみました。ラジオで言っていた感想はまったく覚えていませんが、なんとなく頭に残って、すぐに調べてしまったんです。
好きなものをいろいろな視点から描いているのかな〜、とのんきに読み始めたのが大きな間違いでした。いい意味で、新しい表現の世界に入り込んだような感覚。「好き」なもの、こと、できごと、現象を言葉で表すときに、そのまま言葉にしようとしたら、言葉があふれ出してしまうんだ!と思いました。自然にある山から、噴火するように、いろいろなものが飛び出ししまうイメージ。
もし、言葉の噴火をしながら、私が大好きなカレーについて書こうとしたらどうなるか。まずカレーの話はすぐには出てこない。きっと、、、書き出そうとしても出てこない。ただのカレーの話を書こうとしても、中途半端に、何かが漏れているだけで、また止まってしまいそうになります。それなら、子どものときに、作業療法の訓練でカレーを作ることになって、野菜を切ったことだけは覚えているけれど、味は覚えていないとか、母親が作ったカレーの味はいつでも思い出せるとか、書いてしまうと思います。それがなぜなのか?ともっと深く考えたり、そもそも記憶ってあいまいっていう話になったり、いろいろな方向へ飛んでいきます。いろいろな方向へ飛んでいくけれど、同じ山の上での噴火なので、地面が固まって、山をかたちづくります。いろいろな方向からの話が、まとまるわけではないけれど、紛れもなく「自分」であることを感じました。
そもそも、自分と環境のあいだの「いろいろなできごと」で成り立っているのだとも考えられます。言葉に迷ってしまうことはある意味仕方がないのだと、肩の力が抜けました。
一回読んだだけでは、難解な気がしますが、言わんとしていることを追いたくなるような本でした。